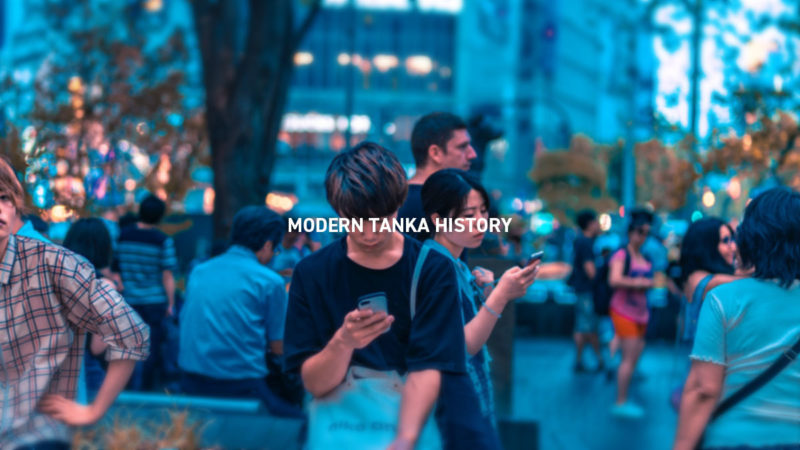
この記事は、現代短歌の特に1995年以降の事件や出来事、あるいは歴史についてまとめたものです。現在に至るまでを年表形式で提供します。
目的
現代において、しかも今もうこの令和の時代において、驚くべきことに短歌を楽しんでいる若い人たちが見受けられます。というよりももう少し何かこう短歌に賭けるものがあるかのように活動的な若い人たちが、目立つように感じられます。
ゼロ年代だとかミレニアル世代だとかZ世代などといった、様々な今の若者を形容する言葉があるようですが、そういえば彼らはこれまでの短歌の歴史に登場したどの世代より、なんとなくでもたしかに異質なものであるかのように見られている気がします。
幼いうちからPC、インターネット、スマホといったものが当たり前のように生活の中にあって、巨大なマスメディアをはじめとした様々な権威は影響力を失っていて、男女はかつてないほど対等で、そんな世界に育ったのであれば、たしかに感じ方や詠い方だって大いに変わってくるのでしょう。
彼らは、今あまりにも急進的な科学の進歩と社会の変容にさらされているのでしょう。いや彼らだけでなく私たちすべてが巻き込まれているはずです。その深刻な力はそれぞれの世代を歴史を思想をズタズタに引き裂いては遠ざけていて、それは気づきにくいけれどでも気づきにくいからこそ、もたらす影響はもしかしたら維新や大戦による分断にも匹敵するものがあるのではないだろうか、とすら思えてきます。
そもそもいつの時代においても若い世代というのは異質に映りがちです。それはそこにたしかに瑞々しい感性と美しい詩情があるからにほかなりません。そんな彼らの生み出す美が間違ってもこの先のさらなる時代のうねりに、孤絶して曝されて擦り減ってしまうなどということは、あってはならないはずです。
できることなら彼らと私たちが、よりしっかりと繋がれるように。これまでとこれからの千年・・・少なくとも100年200年を繋ぐように。振り返る真逆こそが歩むべき方角だと思えるような、これまでの現代短歌が拓いてきた真っすぐな道筋がいつだって見えるように。
いつでもどこでも誰にとってもアクセシブルな現代短歌の年表があれば、もしかしたら少しは援けになるのではないかと思っています。
彼らが、その今触れているシーンと直接的なつながりがある出来事や時代の流れを、ともに見通し、語り合うためのささやかな資料となることを期待して。
Image by Jezael Melgoza on Unsplash
ご協力のお願い
大仰な感じでここまで来ましたが、そもそもこの年表を作る者が、歌学には昏く非才の身にあれば、どうして多くの人に役立つ年表となるでしょうか。
そこで皆様にご協力をお願いしまして、知見や情報の提供、間違いのご指摘などをいただきたく存じます。つきましてはコンタクトフォームまたはTwitterのほうにご連絡いただければ幸いです。
作成する年表の範囲つまりはスタートについて
現代を象徴するテクノロジーであるコンピューターとインターネットが一般社会に、さらには短歌界に浸透しはじめた時期と、近現代の短歌史とともにあった歌誌「アララギ」の終焉の時期が重なるのは、あまりにも印象的です。そこで本記事が記す年表は、アララギの終刊からをその始まりとしたいと思います。
当初はアララギ終刊の97年からと考えていましたが、短歌の世界だけでなく社会全体を大きく変えたインターネットの出現をこそ時代をとらえる範囲のスタート地点と定めるべきと考え、いわゆる「インターネット元年」と呼ばれる1995年からの年表として改め、引き続き随時更新していきたいと思います。
1995年から現在までの現代短歌の年表
1995年
- インターネット元年
- 2人以上世帯のPC普及率は15.6%(内閣府の消費動向調査)
- インターネットの人口普及率の統計は確認できず
| 1.17 | 阪神淡路大震災。被災者情報等の交換にインターネットが活用され注目を浴びる(インターネット元年とも) |
| 3.20 | 地下鉄サリン事件 |
| 7.1 | PHSサービス開始 |
| 8月 | NTT「テレホーダイ」サービス開始 |
| 11.23 | Windows95(日本語版)発売 |
1996年
- PC世帯普及率は17.3%
- インターネットの人口普及率は3.3%(総務省の通信利用動向調査)
- ASAHIネット歌会このころ開設か
- 「歌人メーリングリスト(tk)」このころスタートか
| 3月 | 加藤治郎が個人ホームページ「WAKA」を開設 |
| 4月 | Yahoo! JAPANがサービスを開始 |
| 4月 | 塔短歌会がホームページ開設(短歌結社で初)。この後ごろに続けて中部短歌会がホームページを開設(短歌結社として2例目)し9月までに第1回サイバー歌会を開催(初のネット歌会) |
| 4.3 | 大塚寅彦が個人ホームページ開設 |
| 4.25 | 最初期の短歌ポータル的サイト「短歌ホームページ」(管理人大谷雅彦)の来場者カウント開始日。開設もこの頃か。 |
| 10月 | 塔短歌会が「e歌会」と題してネット歌会を始める |
| 11月 | Windows95(OSR2)の提供始まる。Internet Explorer等のインターネット関連機能が標準装備されていた。これにより日本におけるインターネットの本格的な普及が促進される |
1997年
- この年からいわゆる「出版不況」に入る。前年96年にピークを迎えた出版市場(雑誌だけなら97年がピーク)はこの97年から縮小。雑誌、書籍ともに紙媒体の出版物は現在までほぼ連続して縮小。
- メーリングリスト「現代歌人会議(GK)」このころスタートか
- PC世帯普及率は22.1%
- ネット普及率は9.2%
| 3月 | 短歌人会がホームページを開設(塔、中部短歌会に続いて3例目) |
| 3月 | 「女人短歌」が191号をもって終刊(創刊1949年)。同年12月に資料として192号が刊行される |
| 4.21 | 小林恭二『短歌パラダイス』刊行 |
| 5.8 | 俵万智の第3歌集『チョコレート革命』刊行(36万部を記録) |
| 10月 | 常磐井猷麿「アララギ派」創刊 |
| 10.7 | NIFTY-Serveに「短歌フォーラム」開設(2005年3月12日終了、2月20日に「新・短歌フォーラム」に引き継がれる) |
| 12月 | 「アララギ」12月号をもって終刊(創刊1907年) |
| 12月 | 『CUTiE Comic』(宝島社)に「マスノ短歌教」を連載開始 |
1998年
- 新聞の凋落が始まる。前年97年にピークを迎えた発行部数はこの98年から縮小。朝刊は2009年まで微増が続くが、その後はいずれの新聞も現在までほぼ連続して縮小。
- この年の自殺者は前年の1.7倍に急増し3万人を超える。経済成長率が前年97年から2年連続でマイナス(97年-0.7%、98年-1.9%)となり、バブル崩壊後の不況の影響があらゆる業界や階層、社会全体に到達。
- 加藤治郎、荻原裕幸、穂村弘がエスツープロジェクトを結成
- 第1回フーコー短歌賞(以降第7回まで開催)
| 1月 | 「アララギ」の後継誌として宮地伸一が「新アララギ」を、小暮政次と大河原惇行が「短歌21世紀」を、小市巳世司が「青南」を創刊 |
| 2月 | メーリングリスト「ラエティティア」活動開始 |
| 2.22 | NTTドコモ「iモード」サービス開始 |
| 2.27 | 「電脳短歌イエローページ」開設 |
| 5月 | 立風書房より『新星十人 ―現代短歌ニューウェイブ |
| 6月 | 「心の花」創刊 100年記念号 |
| 7.25 | Windows 98(日本語版)発売 |
| 10.13 | 香川進逝去(「地中海」主宰) |
| 11月 | 中央公論社が読売新聞社に買収される |
| 12.15 | 孤蓬万里(呉建堂)逝去(「台北歌壇(現台湾歌壇)」主宰) |
1999年
| 2月 | NTTドコモが「iモード」のサービスを提供開始。世界で初めて携帯電話でインターネットとe-mailの利用が可能になる |
| 5月 | 「2ちゃんねる」が開設 |
| 6.18 | 「さるさる日記」サービス開始 |
| 12月 | アメリカ・ロサンゼルスの「移植林」解散(創刊1990年) |
| 12月 | 『岩波現代短歌辞典』刊行 |
2000年
- ブロードバンド元年
- 永田淳が「青磁社」(第3次)を創業
- @nifty短歌フォーラムで「歌合2000」が行われる
| 1.26 | 永井陽子逝去(「短歌人」編集委員) |
| 3月 | 西岡徳江が元「移植林」の会員を受け継ぎ「新移植林」を結成 |
| 3.3 | 五十嵐きよみが「梨の実通信」を開設 |
| 4.1 | 荻原裕幸が自身のwebサイト「デジタル・ビスケット」を開設 |
| 4.15 | 穂村弘, 東直子, 沢田康彦『短歌はプロに訊け! |
| 4.15 | 同人誌「パンチマン」創刊 |
| 5月 | NHK『スタジオパークからこんにちは』に枡野浩一を講師として「かんたん短歌塾」はじまる |
| 5月 | メールマガジン「月刊短歌通信ちゃばしら」創刊 |
| 6月 | 三省堂から『現代短歌大事典』刊行 |
| 7月 | 五十嵐きよみによる「梨の実歌会」開設 |
| 7月 | 名古屋で「歌合わせ2000(ミレニアム)」開催。司会に荻原裕幸、判者に岡井隆 |
| 6.29 | メールマガジン「@ラエティティア」創刊 |
| 7.20 | 藤原龍一郎による「短歌発言スペース・抒情が目にしみる」開設 |
| 9.15 | Googleが日本語版のサービスを開始 |
| 9.26 | 穂村弘の「ごーふる・たうん BBS」スタート |
| 10月 | 足立尚彦、森川菜月らによるネット歌会「現代短歌・眩惑の会」のサイトが開設 |
| 10.1 | 藤原龍一郎による「電脳日記・夢見る頃を過ぎても」開設 |
| 11.1 | Amazon.comの日本版サイト「Amazon.co.jp」がオープン |
| 12月 | 枡野浩一『かんたん短歌の作り方 |
| 12.6 | 短歌研究創刊800号記念臨時増刊「うたう」刊行 |
| 12.26 | フレッツADSLの本格提供開始 |
| 12.31 | 「インターネット博覧会(インパク)」開催 |
2001年
- PC世帯普及率が50%を超える(50.1%)
| 1.17 | 「ETV2001・電脳短歌の世界へようこそ」が放映 |
| 3月 | オンデマンド出版の「BookPark(ブックパーク)」で歌集の出版サービス「歌葉(うたのは)」を開始 |
| 3月 | 「短歌研究」2001年4月号より「うたう☆クラブ」スタート |
| 4.15 | 窪田章一郎逝去(「まひる野」主宰) |
| 5月 | Wikipediaの日本語版が発足 |
| 5月 | ネット歌会「眩惑の会」が解散し、松本茂雄、三吉啓二らによる「原人の海図」が引き継ぐ |
| 5.12 | 高瀬一誌逝去(「短歌人」編集・発行人) |
| 7月 | 本間眞人が梧葉出版を創業 |
| 8月 | 加藤千恵の第1歌集『ハッピー☆アイスクリーム |
| 8.19 | 学生短歌大会2001(京大短歌会、早稲田短歌会、東北短歌会の主催で19日~21日の3日間にわたり) |
| 8.31 | 同人誌「パンチマン」が歌合企画「四角いジャングル!炎の五番勝負」における2勝3敗の結果を受け解散。同誌3号をもって終刊 |
| 9月 | 「Yahoo! BB」のサービスを開始 |
2002年
- ネット普及率が50%を超える(57.8%)
- 田島安江が「書肆侃侃房」を創業
- 第1回歌葉新人賞
2003年
- 「短歌WAVE」終刊
| 1月 | 最初の題詠マラソン「題詠マラソン2003」開催される |
| 5月 | 「短歌ヴァーサス」創刊 |
| 5.1 | 隔月刊「短歌朝日」が5・6月号(第36号)で終刊(創刊97年7月号) |
| 5.18 | 高嶋健一逝去(「水甕」運営委員長) |
| 6.1 | 新編国歌大観 CD-ROM ver.2(ver.1は96年8月)発売 |
| 9月 | 最後のワープロ専用機が生産中止に(シャープ「書院」シリーズ) |
| 11.5 | セブンイレブンが「ネットプリントサービス basic」を全国で本運用開始 |
2004年
| 1月 | 読売新聞にて黒瀬珂瀾の「カラン卿の短歌魔宮」の連載が始まる(2006年3月まで) |
| 1.5 | 「梨の実歌会」閉鎖 |
| 2月 | 招待制SNSの「mixi」がプレオープン(3月3日正式オープン) |
| 3月 | 中澤系『uta 0001.txt』刊行 |
| 4月 | 短歌総合新聞『梧葉』創刊(季刊) |
| 4.2 | 「枡野浩一のかんたん短歌blog」が開設される |
| 5.1 | 五十嵐きよみ, 荻原裕幸『短歌、WWW(ウェブ)を走る。―題詠マラソン2003 |
| 5.22 | 春日井建逝去(中部短歌会「短歌」編集発行人) |
| 8.1 | 「六花書林」創業(宇田川寛之) |
| 10月 | 小島なおが第50回角川短歌賞を受賞。当時高校生。18歳2カ月は史上最年少で以降2019年まで破られていない。 |
| 12月 | 季刊「短歌四季」12月号で終刊(短歌四季大賞も4回をもって終了) |
| 12月 | 「短歌ヴァーサス」6号において正岡豊の第1歌集『四月の魚(増補版)』を掲載し誌上復刊 |
2005年
- ネット普及率70%を超える(70.8%)
- 小柳学が左右社を創業
| 3.31 | パソコン通信の「ニフティーサーブ」における「フォーラム」等のコミュニケーションサービスが終了 |
| 4月 | これまでの『NHK歌壇』から『NHK短歌』に名称を変更 |
| 4月 | J-WAVE「笹公人の短歌BLOG」スタート |
| 6.9 | 塚本邦雄死去(「玲瓏」主宰) |
| 10.16 | 笹公人、NHK総合の「日曜スタジオパーク」にレイザーラモンHGの扮装で出演 |
| 12.26 | 『ケータイ livedoor 小説』においてカフェ・ブーム(枡野浩一と佐々木あらら)による青春短歌小説「短歌なふたり」(のちの「ショートソング」)の連載がはじまる |
2006年
- 東京大学本郷短歌会が発足
- この年から「題詠マラソン」が運営方式を変更し「題詠100首blog」となる
- 光森裕樹が短歌ポータル「tankaful」を開設
2007年
- PC世帯普及率70%を超える(71.0%)(以降70%代で微増)
- 「スーパージャンプ」2007年8号から漫画「ショートソング」(原作:枡野浩一, 作画:小手川ゆあ)の連載はじまる
| 1月 | 石川美南らが「さまよえる歌人の会」を結成 |
| 4.30 | 東郷雄二の「今週の短歌」200回を迎え終了 |
| 5月 | 北溟社より『現代短歌最前線―新響十人 |
| 6.19 | YouTubeが日本語版サービスを開始 |
| 9月 | 宮内庁御用掛に岡井隆(8月31日辞の岡野弘彦の後任) |
| 9.30 | 藤原龍一郎による「電脳日記・夢見る頃を過ぎても」終了 |
| 10月 | 「短歌ヴァーサス」11号で終刊 |
| 12.28 | 「ちはやふる」の連載が『BE・LOVE』2008年2号誌上ではじまる |
2008年
- 佐々木あららによる「星野しずる」サービス開始
- 村井光男がナナロク社を創業
| 1月 | 新風舎が民事再生を申請 |
| 2月 | 寺山修司『寺山修司未発表歌集 月蝕書簡 |
| 4.1 | 東郷雄二が『橄欖追放』と題して短歌コラムを再開 |
| 4.5 | 「ダ・ヴィンチ」5月号より穂村弘の「短歌ください」が始まる |
| 4.6 | 『土曜の夜はケータイ短歌』が『夜はぷちぷちケータイ短歌』にリニューアル |
| 4.15 | 季刊「現代短歌雁」66号をもって終刊(1987年1月1日創刊1号) |
| 4.23 | Twitterの日本語版が利用可能に |
| 5月 | Facebookが日本語化されたインターフェイスを公開 |
| 7月 | 雁書館廃業 |
| 7.1 | 河野裕子が歌会始選者に(引退の岡野弘彦に代わり)先任の永田和宏と夫婦で選者となる |
| 11.11 | 短歌投稿サービス「うたのわ」リリース |
| 12.8 | ホームレス歌人公田耕一が朝日歌壇に入選し話題に |
2009年
- 東京外国語大学の「外大短歌会」が発足
2010年
- スマートフォンの本格的な普及がはじまる(キャリアのサービス強化、日本メーカーによる高性能機種の市場投入)
- 大阪大学の阪大短歌会が発足
| 3月 | 「短歌」(中部短歌会)が電子書籍に対応し、webサイト上でPDFによる初の歌誌(見本誌)公開 |
| 3.1 | SNSの「mixi」が招待状無しで登録可能に |
| 3.30 | 竹山広逝去(「心の花」) |
| 6月 | 田中ましろが短歌×写真のフリーペーパー「うたらば」を創刊(6月にvol.00見本号(創刊準備号)、11月にvol.01創刊号) |
| 7.19 | 天野慶、村田馨ら2人の歌人と5人の写真家による「写真と短歌のコラボ展『FanTastiC生命の輝き』」が開催(~25日) |
| 8.12 | 河野裕子逝去(「塔」選者) |
| 9.15 | 現代歌人協会公開講座「対決!現代短歌の前線II ネット系VS結社系」が開催(パネリスト:ネット系=枡野浩一、加藤千恵、結社系=加藤治郎、花山周子、コーディネーター:穂村弘) |
| 12月 | 季刊「短歌苑」通巻5号を最終号として終刊 |
2011年
| 2.24 | 石田比呂志逝去(「牙」(第2次)主宰)遺言により「牙」も終刊 |
| 3.11 | 東日本大震災 |
| 4.8 | 天野うずめがUstreamを利用した「Uスト歌会(後の歌会たかまがはら)」の第1回を開催(以降定期開催を続けるも2020年2月開催を最後に休止) |
| 4.16 | 宮地伸一逝去(「新アララギ」代表) |
| 4.21 | 森川雅美が三詩型交流企画サイトの「詩客 SHIKAKU」を開設 |
| 6.30 | 「さるさる日記」サービス終了 |
| 7.13 | 「Uスト歌会」が第4回から「歌会たかまがはら」と改称 |
| 8.6 | 小島なおの同名歌集を原作とした映画「乱反射」が公開 |
| 9月 | 嶋田さくらこらによる「短歌なzine うたつかい」創刊 |
| 10月 | 立花開が第57回角川短歌賞を受賞。小島なお以来の高校生18歳での受賞 |
| 10.24 | 村上きわみがネットプリントによる短歌の豆本「まめきわみ」を発行 |
| 11月 | 「短歌新聞(698号)」「短歌現代(418号)」がそれぞれ12月号をもって終刊。これにともない発行元の短歌新聞社も解散の方針 |
| 11月 | 元短歌新聞社「短歌現代」編集長の玉城入野が「いりの舎」を設立 |
| 11.3 | 歌集『町』刊行。これを成果として同人誌「町」は解散。最終号は4号(’10年12月5日刊) |
| 11.5 | 雑食がネットプリントによるフリーペーパー(12首)を発行 |
| 11.23 | 映画「ひとつの歌」が公開(監督:杉田協士、出演:桝野浩一) |
| 12.13 | 青山ブックセンター本店にて「穂村弘VS枡野浩一 ブックデザイン自慢合戦!」が開催 |
| 12.24 | 第1回「牧水・短歌甲子園」が開催 |
2012年
| 1月 | 「八雁短歌会」結成。阿木津英を中心に元「牙」および「あまだむ」が合流。 |
| 3月 | 「短歌新聞社」解散 |
| 3月 | 現代短歌社を設立(道具武志) |
| 4月 | いりの舎の「うた新聞」創刊 |
| 4月 | 現代短歌社の「現代短歌新聞」創刊 |
| 4.1 | NHKラジオ番組「夜はぷちぷちケータイ短歌」放送終了 |
| 4.1 | 「NHK短歌」第4週放送分が「短歌de胸キュン」にリニューアル |
| 5月 | 金井美恵子が『KAWADE道の手帖 深沢七郎』誌上に「たとへば(君)、あるいは、告白、だから、というか、なので、『風流夢譚』で短歌を解毒する」と題して短歌批判を展開 |
| 5.6 | 同人誌「率」創刊。前年解散の同人誌「町」のメンバーらによる。 |
| 5.24 | 当時のフォーラムなどを再現した新「NIFTY-Serve」が1年間限定で提供開始 |
| 7.19 | 「楽天 kobo イーブックストア |
| 10月 | Amazonが『Kindleストア |
| 10.13 | 「短歌をカネにかえたくて ―『もしニーチェが短歌を詠んだら』重版祈念トークライブ―」(中島裕介、佐々木あらら)が開催 |
| 11.18 | 第15回文学フリマにてBL短歌合同誌『共有結晶』が創刊 |
| 11.18 | 吉田恭大がネットプリント「全く新しい効能を持つ都市間交通システム(仮称)」を発行 |
| 12.24 | 村上きわみ、石畑由紀子、氏橋奈津子がネットプリント折り本歌集「ピヌピヌ」を発行 |
| 12.25 | 新編国歌大観 DVD-ROM版 発売 |
| 12.27 | 千原こはぎがネットプリントによる折り本プチ歌集『硝子質』を発行 |
| 12.31 | Twitter上のイベント「紅白短歌合戦」が初開催(2012~14までの3回。前日30日には前夜祭も) |
2013年
- ネット普及率80%を超える(82.8%)(以降80ラインを増減)
- スマートフォンの普及率50%を超える(62.6%)(総務省の通信利用動向調査)
- 同人誌「開放区」終刊(創刊1983年)
| 1.27 | 石黒清介逝去(「短歌新聞社」社長) |
| 3.17 | ぺんぎんぱんつ(しんくわ、田丸まひる)によるネットプリント『ぺんぎんぱんつの紙』が発行、以降現在(2019年32号)まで続く |
| 5.25 | 書肆侃侃房から「新鋭短歌シリーズ」刊行開始 |
| 4.8 | 水甕創刊100年記念全国大会が開催(創刊1914年4月) |
| 4.14 | 「文学フリマ」の第16回開催が大阪で(定例開催としては東京以外では初)以降各地に事務局を設立し規模を広げていく |
| 4.14 | 第16回文学フリマにて「短歌男子」刊行(男性歌人10人のスーツグラビアと短歌アンソロジー) |
| 4.18 | 「現代短歌 歌葉」サイト閉鎖 |
| 7.1 | 「未来短歌会」が一般社団法人となる。短歌結社において初例か。 |
| 7.20 | 村上きわみ、平田俊子、島なおみ、今井聡、田中槐ら蟹座生まれの歌人5人によるネットプリント折り本『蟹座』が発行 |
| 8月 | 歌誌「白鳥」が成瀬有追悼特集号をもって終刊(創刊94年) |
| 8.14 | 現代短歌社の「現代短歌」創刊 |
| 8.26 | 「うたよみん」ベータ提供開始 |
| 10.25 | 文化功労者に岡野弘彦 |
| 12.19 | pixivがネットショップ無料作成サービス「BOOTH」を開始 |
2014年
- コスモス内勉強会「桟橋」解散
| 1.12 | 大阪でBL短歌オフイベント「BL-TANKA PRESENTATION」が開催 |
| 2月 | 短歌結社「なんたる星」が発足 |
| 2.10 | 小高賢逝去(「かりん」) |
| 3月 | フランス・パリに「パリ短歌クラブ」発足 |
| 4.1 | の子による歌会サイト「うたの日」サービス開始 |
| 4.7 | 文章等の有料配信を可能とするwebサイト「note(ノート)」がサービス開始 |
| 7.1 | 今野寿美が歌会始選者に(引退の岡井隆に代わり)先任の三枝昂之と夫婦で選者となる(永田河野夫婦に次ぎ2例目) |
| 7.19 | 「大阪短歌チョップ」が開催される |
| 8.25 | 「短歌ポータル tankaful(タンカフル)」がリニューアル |
| 9.20 | 『短歌研究』10月号に加藤治郎の「虚構の議論へ 第57回短歌研究新人賞受賞作に寄せて」掲載(石井僚一作品の虚構問題) |
| 12月 | 「葉ね文庫」開店 |
| 12.31 | Twitter上の年越し短歌ライブイベント「CDTNK(カウントダウン短歌)」の初めての開催 |
2015年
- スマホ普及率70%を超える(72.0%)
- コスモス内若手勉強会「COCOONの会」発足、2016年より年4回「COCOON」発行(発行人:大松達知)
| 3.1 | 大学短歌バトル2015が開催(ニコニコ生放送で中継も。以降恒例開催となり本開催が第1回に) |
| 3.25 | 「短歌」4月号からはじまる「水仙と盗聴」論争 |
| 3.30 | 笹公人の『念力家族 |
| 4.14 | 書肆侃侃房から「現代歌人シリーズ」刊行開始 |
| 6.26 | 宮英子逝去(「コスモス」発行人) |
| 7月 | 「潮音」創刊百周年記念号刊行 |
| 11月 | 谷じゃこが短歌であそぶフリーペーパー「バッテラ」を創刊 |
| 11月 | 石井僚一が自ら石井僚一短歌賞を創設。以降第2回まで開催 |
| 12.24 | 山田航編集のアンソロジー『桜前線開架宣言 |
| 12.28 | 「しんぶん赤旗」の選者に歌会始選者でもある今野寿美が就任 |
2016年
- 1976年から続く「雑高書低」が41年ぶりに逆転
- 「題詠blog」が「題詠100」と名を改めFacebookを利用する方式へ変更
| 2.9 | 鳥居の第1歌集『キリンの子 |
| 2.14 | 名古屋の中華料理店「平和園」のノート「炒飯と餃子と唐揚げ」に千種創一が書き込み第1号 |
| 2.23 | 株式会社アルヴェアーレが無料短歌投稿アプリ「ちどり 短歌会」をリリース |
| 4.4 | TVドラマ「念力家族」第2シーズンがスタート |
| 4.17 | 石井僚一の運営による「ネットプリント毎月歌壇」が創刊4月号を配信開始。選者に石井僚一、谷川電話 |
| 8月 | 武田穂佳が第59回短歌研究新人賞を受賞。18歳9か月は寺山修司(18歳11か月)を抜いて史上最年少。 |
| 8.4 | Amazonが、電子書籍読み放題サービス『Kindle Unlimited |
| 8.20 | 高校生万葉短歌バトル2016(第1回高校生万葉短歌バトルin高岡)が開催 |
| 9.25 | 文学フリマ大阪にてなべとびすこによる短歌カードゲーム「ミソヒトサジ」が販売される |
| 10.1 | 現代短歌社が出版する歌集の売り上げの一部を全国コミュニティ財団協会に寄付するプログラムを開始 |
| 10.1 | 朗読イベント「短歌マイクロフォン」(主催:フラワーしげる(西崎憲))が吉祥寺シェモアにて開催 |
| 10.25 | カン・ハンナが第62回角川短歌賞で佳作に。外国語を母語とする者としては初めての入選 |
| 10.26 | 文化功労者に岡井隆 |
| 12月 | 月刊オカルト情報誌「ムー」にて「オカルト短歌」(選者:笹 公人、絵:石黒亜矢子)がスタート |
| 12.23 | 「かばん」2016年12月号 |
| 12.12 | 「小説 野生時代」(第158号 2017年1月号)誌上において「野生歌壇」がスタート。選者に山田航と加藤千恵 |
2017年
| 1.21 | 朗読イベント「短歌マイクロフォン2」(主催:フラワーしげる(西崎憲))が吉祥寺シェモアにて開催 |
| 2.25 | 「大阪短歌チョップ vol.2」が開催される |
| 2.25 | 「大阪短歌チョップ vol.2」で先行版を改定した「ミソヒトサジ〈定食〉」が販売される |
| 3.3 | 清水房雄逝去(「青南」編集委員) |
| 4月 | 株式会社現代短歌社が解散(団体名としては存続)その事業譲渡を受けて三本木書院(真野少)が発足 |
| 4月 | 「塔短歌会」が一般社団法人となる。2013年の「未来短歌会」に続いて2例目か。 |
| 6.8 | 萩原慎一郎逝去(「りとむ」) |
| 7.23 | 桝野浩一がCAMPFIREにて「世界初Tシャツ歌集をつくりたい!『MASUNOTANKA20TH』」としてクラウドファンディングを実施。最終的に210万円余を集め目標額の370%を達成 |
| 8.5 | CDTNK(カウントダウン短歌)の夏季イベントとして「CDTNK夏フェス」を初開催 |
| 10.31 | 「恋愛短歌同好会会報 ショート(ケーキ)ソング vol.1」がネットプリントによる折本として発行される |
| 12.17 | 恋愛短歌同好会における第1回目の公開合評会キャス配信が開かれる。翌18日にはその結果が公開される |
| 12.26 | 萩原慎一郎の第1歌集『滑走路 |
| 12.31 | 東京大学本郷短歌会が解散。機関誌は16年5月24日に発売された第五号が最終 |
2018年
| 1.7 | 木下龍也, 岡野大嗣共著の歌集「玄関の覗き穴から差してくる光のように生まれたはずだ |
| 1.28 | 東直子, 佐藤弓生, 千葉聡編集のアンソロジー『短歌タイムカプセル |
| 3月 | 「桜狩」が184号を持って終刊(創刊1985年) |
| 3月 | 鈴木智子がクラウドファンディングで歌集出版の支援を募る。プレスリリースも活用するなどするも、最初のMOTION GALLERYでの募集は目標未到達に終わる。その後FAVVOで目標額を達成。この支援を受け12月に歌集『砂漠の庭師』を刊行 |
| 4.1 | 新編国歌大観 ジャパンナレッジ版(オンライン版)発売 |
| 5.1 | 宮内庁御用掛に篠弘(4月30日辞の岡井隆の後任) |
| 5.18 | 書肆侃侃房が「笹井宏之賞」を創設 |
| 6.2 | 『現代短歌シンポジウム ニューウェーブ30年「ニューウェーブは、何を企てたか」』(パネリスト:荻原裕幸、加藤治郎、西田政史、穂村弘)が開催 |
| 8月 | 川谷ふじのが第61回短歌研究新人賞を受賞。高校生で初。また17歳9か月は同賞だけでなく主要新人賞受賞者の中でも最年少であるとともに2000年代生まれの受賞者というのも初めてのこと |
| 8.18 | 高村七子が東京浅草の古民家風ダイニングバー「安寿」にて「俳句・短歌カフェ17・31」を開催(19日まで) |
| 8.22 | 音楽の夏フェスを模したTwitter上のイベント「TANKASONIC(タンカソニック2018)」が開催 |
| 9.15 | 塔短歌会が塔の2018年9月号にて「セクシュアル・ハラスメント防止の取り組みと相談窓口の開設について」とし対応窓口の設置を宣言。 |
| 9.29 | 「本のあるところ ajiro」プレオープン(正式オープンは10月6日) |
| 10.19 | 紀伊茶屋京橋店にて書肆侃侃房の協力により「短歌カフェ with 紀伊茶屋」を開催(11月15日まで) |
| 12月 | 石井僚一が歌の別れを宣言 |
| 12.4 | 短歌×写真のフリーペーパー「うたらば」が日本タウン誌フリーペーパー大賞2018のコミュニティ・ライフスタイル部門にて「最優秀賞」を受賞 |
| 12.8 | 西岡徳江逝去(「新移植林」主宰)「新移植林」も12月号をもって終刊 |
2019年
| 1.2 | NHK BSプレミアムで「平成万葉集」(主演:生田斗真, 吉岡里帆、監修:永田和宏)のプロローグ回が放送(以降5月1日まで全4回) |
| 1.12 | 短歌をテーマにした映画「ひかりの歌」の公開が始まる(監督:杉田協士、原作短歌の選考に枡野浩一が参加) |
| 2.28 | 「はてなダイアリー」サービス終了 |
| 3.17 | 「ネットプリント毎月歌壇」が3月号の配信をもって終了 |
| 3.31 | 「Yahoo!ジオシティーズ」サービス終了 |
| 4.30 | webマガジン「TANKANESS」開始 |
| 4.30 | 「Google+」サービス終了 |
| 5.1 | 令和に改元(第125代天皇から第126代天皇への譲位にともない) |
| 6.25 | 「『玄関の覗き穴から差してくる光のように生まれたはずだ』展」開催(~7月7日) |
| 9.17 | 歌誌「創作」9月号をもって終刊(創刊1910年) |
| 10.29 | 文化功労者に馬場あき子 |
| 11.16 | 現代短歌社の「現代短歌」が2020年1月号(76号)より月刊から隔月刊となる |
| 11.30 | 未来短歌会の理事会において、選者のハラスメントに関わる事案が理事の一人から提議。協議の結果、ハラスメントに関する委員会、相談会等を設置するべく検討し、防止に努めることに。 |
| 12月 | カナダの「バンクーバー短歌会」が解散(設立1985年) |
| 12.15 | 「Yahoo!ブログ」サービス終了 |
2020年
| 1.12 | 未来短歌会にハラスメント委員会が発足。1月19日に相談窓口を設置。 |
| 1.29 | 山本かね子逝去 |
| 2.27 | 「短歌往来 |
| 4.7 | 新型コロナウイルスの感染拡大を受け7都府県に「緊急事態宣言」が発令。多くの歌会や短歌関連のイベントが中止や延期を余儀なくされる |
| 4.22 | 「短歌研究 |
| 5月 | 「最適日常」が短歌情報サイトとしての活動を開始 |
| 6.9 | 冷泉家が古文書等を保存する土蔵建設の資金を募るためクラウドファンディングを実施。目標額の350万円を1日で達成、6月12日には1千万円を超える。 |
| 6.10 | 京都の書店「三月書房」が閉店(廃業は12月末) |
| 6.25 | 石川不二子逝去(報道では25日ごろ。正確な日時は不明) |
| 7.8 | 『ホスト万葉集 嘘の夢嘘の関係嘘の酒こんな源氏名サヨナライツカ』(短歌研究社) |
| 7.10 | 岡井隆逝去(「未来」編集委員長) |
| 8.8 | NTTレゾナントと短歌研究による「恋するAI歌人」を公開(同年9月9日までの限定公開)(※関連記事) |
| 9.30 | キュレーションサイト「NAVERまとめ」がサービスを終了 |
| 10.26 | 10月1日に官房記者会見で明らかになった「日本学術会議の任命拒否問題」に対し「現代歌人協会」と「日本歌人クラブ」の2団体が共同で「日本学術会議の新会員任命拒否に反対する声明」を発表 |
| 11.20 | 映画『滑走路』が全国公開される。 |
| 12.23 | 嶋稟太郎が「推したい短歌2020」を開催。以降形を変えながら |
2021年
| 2.21 | 第1回「オンライン短歌市」開催 |
| 3月 | 「あみもの」(御殿山みなみ)が39号をもって終刊 |
| 3月 | 「うたそら」(千原こはぎ)創刊 |
| 5.12 | 「短歌研究」5月号が重版に。創刊以来初めてのこと(初版4000部。5月12日に2刷・500部、6月2日に3刷・1000部が出来) |
| 6月 | 『はつなつみずうみ分光器 after 2000 現代短歌クロニクル』(左右社) |
| 7月 | 「西瓜」創刊 |
| 7月 | 角川武蔵野ミュージアムで「俵万智 展 #たったひとつの「いいね」 『サラダ記念日』から『未来のサイズ』まで」が開催。当初11月までの会期は2度の延長を重ね、明けて2022年の1月まで展かれる。 |
| 7月 | なべとびすこによるカードゲーム『57577 ゴーシチゴーシチシチ』(幻冬舎)発売 |
| 7.6 | 第1回「アイドル歌会@サラダ記念日」開催(以降この年だけで計4回開催を重ねる) |
| 8.29 | 第2回「オンライン短歌市」開催 |
| 9月 | 「うたつかい」(嶋田さくらこ)が36号をもって終刊 |
| 9.1 | この時期「tankalife.net」が活動を始める(この日が日付を確認できる最初の記事) |
| 11月 | 岡野弘彦に文化勲章(歌人としての活動が顕著な人物としては土屋文明に続いて4人目) |
| 11月 | 典々堂が開業 |
| 12月 | 『岡野弘彦全集』(青磁社) |
| 12.18 | 連句人の高松霞が、短詩界のセクハラ問題を扱った「短歌・俳句・連句の会でセクハラをしないために」パンフレットを制作するためのクラウドファンディングを開始(3日で目標額の30万を達成し、5日でネクストゴールの40万を達成) |
2022年
| 3.16 | 高松霞が、プロジェクト「短歌・俳句・連句の会でセクハラをしないために」を発足。短詩の団体や結社に要望書を送付するなどの活動を開始 |
| 6月 | 点滅社が開業 |
| 10.3 | NHK「連続テレビ小説」で歌人を登場人物に据えた「舞いあがれ!」放送開始 |
| 10.4 | 野樹かずみが、「去年亡くなった歌人、蝦名泰洋さんの歌集を出版したい」としてクラウドファンディングを開始。目標額60万円を達成し歌集の出版に到る。 |
| 10.28 | イーロン・マスクによりTwitterが買収される |
| 11.7 | 第1回 ジェロニモ短歌賞(「梅ジェロ王決定戦」における企画にて) |
2023年
| 1.28 | はたらきアリ出版が、現代詩歌のプラットフォーム「suiu」が公開 |
| 3.22 | 「短歌研究」2023年4月号で拡大特集 「短歌の場でのハラスメントを考える」 |
| 5.7 | 深水英一郎がこの日を「短歌の日」として提案。以降毎年様々な企画を行う。 |
| 5.29 | 『トビウオが飛ぶとき 「舞いあがれ!」アンソロジー』桑原亮子(KADOKAWA)刊行 |
| 6.16 | 深水英一郎が「第0回 AI歌壇」(その後の「毎月短歌」)の募集を開始。その後第1回に受け継がれ定期開催へ。 |
| 7.24 | TwitterがXに名称変更 |
| 9月 | 深水英一郎がA短歌会の活動をはじめる |
| 10.8 | 「AI歌壇」が「毎月短歌」へ名称変更(第4回から。ナンバリングは継承) |
2024年
| 1.19 | 講談社の「コミックDAYS」において、本格的な現代短歌、歌人を扱った漫画連載『呪文よ世界を覆せ』ニコ・ニコルソンが連載開始 |
| 7.1 | 鈴木智順が、短歌アプリ『57577』Android版リリース |
| 9.4 | ピクシブ株式会社のサービス「pixivFANBOX」がシャープ製マルチコピー機にて、「FANBOXプリント」のサービスを提供開始 |
| 12.20 | 「短歌研究」2025年1月・2月合併号から隔月刊に。 |
2025年
| 2.4 | 深水英一郎が主催する「A短歌会」が「次世代短歌会」へ名称統一 |
| 5.7 | 株式会社東京ドームが、ことばの投稿・閲覧SNS「コトアム」リリース |
情報提供およびご指摘等ありましたら、コンタクトフォームまたはX(旧Twitter)のほうにご連絡ください。
参照させていただいたサイト等
1995年から短歌界の出来事を収集するために、特に参照させていただいたサイトをここに記し御礼申し上げます。
- 内野光子のブログ
- 銀河最終便
- 笹公人 公式ページ
- 電脳短歌イエローページ
- Internet Archive
- DISITAL BISCUIT
- Twitter上の数多くのツイート





