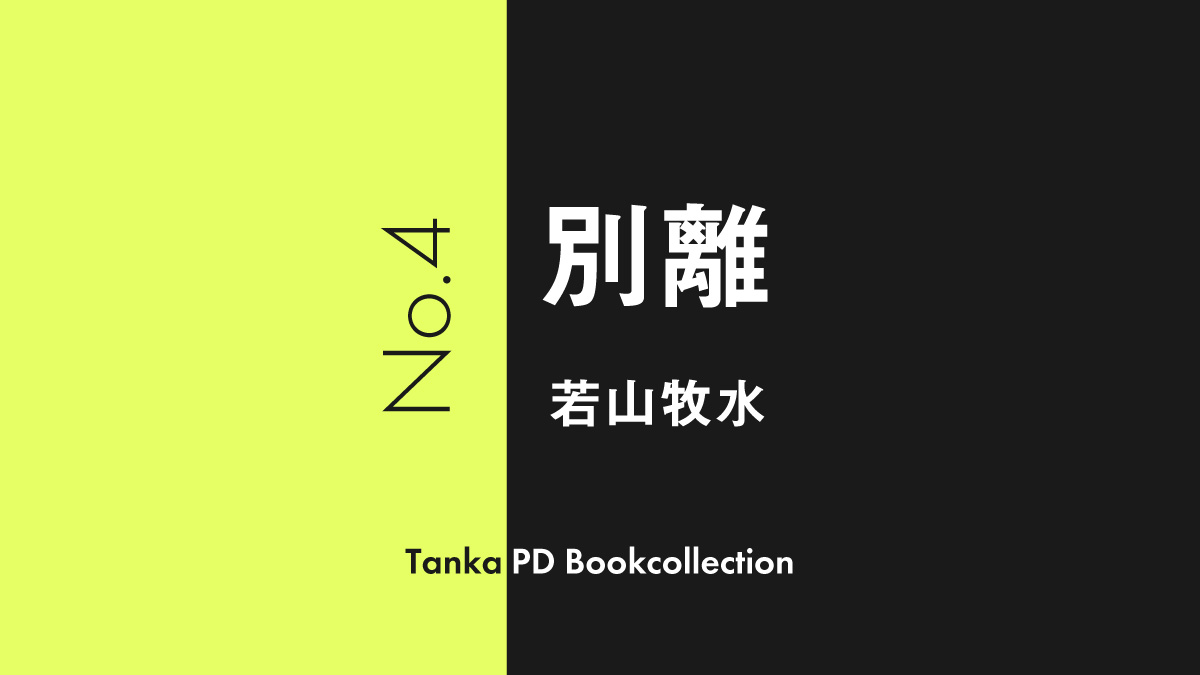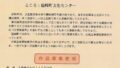この記事では、現代短歌PD文庫の一つとして若山牧水の歌集『別離』の全文をHTMLで提供するものです。
底本情報
- 底本:国立国会図書館デジタルコレクション1883090
- タイトル:牧水全集 第一巻 集録 別離 上巻、下巻
- 著者:若山牧水(1928年没 > 1979年公有化)
- 出版者:改造社
- 出版年月日:1929年(昭和4年)11月8日
初出は次の通りです。
- タイトル:別離 上巻、下巻
- 出版者:東雲堂書店
- 出版年月日:1910年(明治43年)4月10日
別離
自序
廿歳頃より詠んだ歌の中から一千首を抜き、一巻に輯めて『別離』と名づけ、今度出版することにした。昨日までの自己に潔く別れ去らうとするこころに外ならぬ。
先に著した『独り歌へる』の序文に私は、私の歌の一首一首は私の命のあゆみの一歩一歩であると書いておいた。また、一歩あゆんでは小さな墓を一つ築いて来てゐる様なものであるとも書いておいた。それらの歌が背後につづいて居ることは現在の私にとつて、可懐しくもまた少なからぬ苦痛であり負債である。如何かしてそれらと絶縁したいといふ念願からそれを一まとめにして留めておかうとするのである。然うして全然過去から脱却して、自由な、解放された身になつて今まで知らなかつた新たな自己に親しんで行き度いとおもふ。
また、昨年あたりで私の或る一期の生活は殆んど名残なく終りを告げて居る。そして丁度昨年は人生の半ばといふ廿五歳であつた。それやこれや、この春この『別離』を出版しておくのは甚だ適当なことであると私は歓んで居る。
本書の装幀一切は石井柏亭氏を煩はした。写真は一昨年の初夏に撮つたものである。この一巻に収められた歌の時期の中間に位するものなので挿入しておいた。
歌の掲載の順序は歌の出来た時の順序に従うた。
左様なら、過ぎ行くものよ。これを期として我等はもう永久に逢ふまい。
明治四十三年四月六日
著者
上巻 自明治三十七年四月 至同四十一年三月
水の音に似て啼く鳥よ山ざくら松にまぢれる深山の昼を
なにとなきさびしさ覚え山ざくら花ちるかげに日を仰ぎ見る
山越えて空わたりゆく遠鳴の風ある日なりやまざくら花
朝地震す空はかすかに嵐して一山白きやまざくらばな
行きつくせば浪青やかにうねりゐぬ山ざくらなど咲きそめし町
朝の室夢のちぎれの落ち散れるさまにちり入る山ざくらかな
阿蘇の街道大津の宿に別れつる役者の髪の山ざくら花
母恋しかかるゆふべのふるさとの桜咲くらむ山の姿よ
父母よ神にも似たるこしかたに思ひ出ありや山ざくら花
春は来ぬ老いにし父の御ひとみに白ううつらむ山ざくら花
怨みあまり切らむと云ひしくろ髪に白躑躅さすゆく春のひと
忍草雨しづかなりかかる夜はつれなき人をよく泣かせつる
山脈や水あさぎなるあけぼのの空をながるる木の香かな
日向の国むら立つ山のひと山に住む母恋し秋晴の日や
君が背戸や暗よりいでてほの白み月のなかなる花月見草
蛼や寝ものがたりの折り折りに涙もまぢるふるさとの家
秋あさし海ゆく雲の夕照りに背戸の竹の葉うす明りする
朝寒や萩に照る日をなつかしみ照らされに出し黒かみのひと
別れ来て船にのぼれば旅人のひとりとなりぬはつ秋の海
秋風は木の間に流る一しきり桔梗色してやがて暮るる雲
白桔梗君とあゆみし初秋の林の雲の静けさに似て
思ひ出れば秋咲く木木の花に似てこころ香りぬ別れ来し日や
秋立ちぬわれを泣かせて泣き死なす石とつれなき人恋しけれ
この家は男ばかりの添寝ぞとさやさや風の樹に鳴る夜なり
木の蔭や悲しさに吹く笛の音はさやるものなし野にそらに行く
吾木香すすきかるかや秋くさのさびしききはみ君におくらむ
秋晴や空にはたえず遠白き雲の生れて風ある日なり
秋の雲柿と榛との樹樹の間にうかべるを見て人も語らず
幹に倚り頬をよすればほのかにも頬に脈うつ秋木立かな(※原書は「秋立木」)
机のうへ植木の鉢の黒土に萌えいづる芽あり秋の夜の灯よ
秋の灯や壁にかかれる古帽子袴のさまも身にしむ夜なり
富士よゆるせ今宵は何の故もなう涙はてなし汝を仰ぎて
日が歩むかの弓形のあを空の青ひとすぢのみちのさびしさ
悲しさのあふるるままに秋のそら日のいろに似る笛吹きいてむ
山ざくら花のつぼみの花となる間のいのちの恋もせしかな
淋しとや寂しきかぎりはてもなうあゆませたまへ如何にとかせむ (人へかへし)
うらこひしさやかに恋とならぬまに別れて遠きさまざまの人
ぬれ衣のなき名をひとにうたはれて美しう居るうら寂しさよ
春たてば秋さる見ればものごとに驚きやまぬ瞳の若さかな
町はづれきたなき溝の匂ひ出るたそがれ時をみそさざい啼く
植木屋は無口のをとこ常磐樹の青き葉を刈る春の雨の日
船なりき春の夜なりき瀬戸なりき旅の女と酌みしさかづき
春の森青き幹ひくのこぎりの音と木の香と藪うぐひすと
ただひとり小野の樹に倚り深みゆく春のゆふべをなつかしむかな
わだつみのそこひもわかぬわが胸のなやみ知らむと啼くか春の鳥
ゆく春の月のひかりのさみどりの遠をさまよふ悲しき声よ
雲ふたつ合はむとしてはまた遠く分れて消えぬ春の青ぞら
眼とづればこころしづかに音をたてぬ雲遠見ゆる行く春のまど
鶯のふと啼きやめばひとしきり風わたるなり青木が原を
椎の樹の暮れゆく蔭の古軒の柱より見ゆ遠山を焼く
春来ては今年も咲きぬなにといふ名ぞとも知らぬ背戸の山の樹
町はづれ煙筒もるる青煙のにほひ迷へる春木立かな
われはいま暮れなむとする雲を見る街は夕の鐘しきりなり
淋しくばかなしき歌のおほからむ見まほしさよと文かへし来ぬ
人どよむ春の街ゆきふとおもふふるさとの海の鷗啼く声
街の声うしろに和むわれらいま潮さす河の春の夜を見る
春の夜や誰ぞまだ寝ぬ厨なる甕に水さす音のしめやかに
春の夜の月のあはきに厨の戸誰が開けすてし灯のながれたる
日は寂し万樹の落葉はらはらに空の沈黙をうちそそれども
見よ秋の日のもと木草ひそまりていま凋落の黄を浴びむとす
鍬をあげまた鍬おろしこつこつと秋の地を掘る農人どもよ
うすみどりうすき羽根着るささ虫の身がまへすあはれ鳴きいづるらむ
うつろなる秋のあめつち白日のうつろの光ひたあふれつつ
秋真昼青きひかりにただよへる木立がくれの家に雲見る
落日や街の塔の上金色に光れど鐘はなほ鳴りいてず
啼きもせぬ白羽の鳥よ河口は赤う濁りて時雨晴れし日
さらばとてさと見合せし額髪のかげなる瞳えは忘れめや (二首秀嬢との別れに)
別れてしそのたまゆらよ虚なる双のわが眼にうつる秋の日
いま瞑ぢむ寂しき瞳明らかに君は何をかうつしたりけむ (途中大阪にかれは逝きぬ)
短かりし君がいのちのなかに見ゆきはまり知らぬ清きさびしさ
窓ちかき秋の樹の間に遠白き雲の見え来て寂しき日なり
酒の香の恋しき日なり常盤樹に秋のひかりをうち眺めつつ
見てあれば一葉先づ落ちまた落ちぬ何おもふとや夕日の大樹
をちこちに乱れて汽笛鳴りかはすああ都会よ見よ今日もまた暮れぬ
海の声断えむとしてはまた起る地に人は生れまた人を生む
人といふものあり海の真蒼なる底にくぐりて魚をとりて食む
山茶花は咲きぬこぼれぬ逢ふを欲りまたほりもせず日経ぬ月経ぬ
遠山の峰の上にきゆるゆく春の落日のごと恋ひ死にも得ば
秋の夜やこよひは君の薄化粧さびしきほどに静かなるかな
世のつねのよもやまがたり何にさは涙さしぐむ灯のかげの人
君去にてものの小本のちらばれるうへにしづけき秋の灯よ
いと遠き笛を聴くがにうなだれて秋の灯のまへものをこそおもへ
相見ればあらぬかたのみうちまもり涙たたえしひとの瞳よ
君は知らじ君の馴寄るを忌むごときはかなごころのうらさびしさを
落葉焚くあをきけむりはほそほそと木の間を縫ひて夕空へ行く
静けさや君が裁縫の手をとめて菊見るさまをふと思ふとき
相見ねば見む日をおもひ相見ては見ぬ日を思ふさびしきこころ
ふとしては君を避けつつただ一人泣くがうれしき日もまぢるかな
黄に匂ふ悲しきかぎり思ひ倦じ対へる山の秋の日のいろ
一葉だに揺れず大樹は夕ぐれのわが泣く窓に押しせまり立つ
旅ゆきてうたへる歌をつぎにまとめたり、思ひ出にたよりよかれとて
山の雨しばしば軒の椎の樹にふりきてながき夜の灯かな (百草山にて)
立川の駅の古茶屋さくら樹の紅葉のかげに見おくりし子よ
旅人は伏目にすぐる町はづれ白壁ぞひに咲く芙蓉かな (日野にて)
家につづく有明白き萱原に露さはなれや鶉しば啼く
あぶら灯やすすき野はしる雨汽車にほほけし顔の十あまりかな
戸をくれば朝寝の人の黒かみに霧ながれよる松なかの家 (三首御嶽にて)
霧ふるや細目にあけし障子よりほの白き秋の世の見ゆるかな
霧白ししとしと落つる竹の葉の露ひねもすや月となりにけり
野の坂の春の木立の葉がくれに古き宿見ゆ武蔵の青梅
なつかしき春の山かな山すそをわれは旅びと君おもひ行く
思ひあまり宿の戸押せば和やかに春の山見ゆうち泣かるかな
地ふめど草鞋声なし山ざくら咲きなむとする山の静けさ
山静けし峰の上にのこる春の日の夕かげ淡しあはれ水の声
春の夜の匂へる闇のをちこちによこたはるなり木の芽ふく山
汽車過ぎし小野の停車場春の夜を老いし駅夫のたたずめるあり
日のひかり水のひかりの一いろに濁れるゆふべ大利根わたる
大河よ無限に走れ秋の日の照る国ばらを海に入るなかれ
松の実や楓の花や仁和寺の夏なほわかし山ほととぎす (京都にて)
けふもまたこころの鉦をうち鳴しうち鳴しつつあくがれて行く (九首中国を巡りて)
海見ても雲あふぎてもあはれわがおもひはかへる同じ樹蔭に
幾山河越えさり行かば寂しさの終てなむ国ぞ今日も旅ゆく
峡縫ひてわが汽車走る梅雨晴れの雲さはなれや吉備の山山
青海はにほひぬ宮の古ばしら丹なるが淡う影うつすとき (宮島にて)
はつ夏の山のなかなるふる寺の古塔のもとに立てる旅びと (山口の瑠璃光寺にて)
桃柑子芭蕉の実売る磯街の露店の油煙青海にゆく (下の関にて)
あをあをと月無き夜を満ちきたりまたひきてゆく大海の潮 (日本海を見て)
旅ゆけば瞳痩するかゆきずりの女みながら美からぬはなし
安芸の国越えて長門にまたこえて豊の国ゆき杜鵑聴く (二首耶馬渓にて)
ただ恋しうらみ怒りは影もなし暮れて旅籠の欄に倚るとき
白つゆか玉かとも見よわだの原青きうへゆき人恋ふる身を (二十三首南日向を巡りて)
潮光る南の夏の海走り日を仰げども愁ひ消やらず
わが涙いま自由なれや雲は照り潮ひかれる帆柱のかげ
檳榔樹の古樹を想へその葉蔭海見て石に似る男をも (日向の青島より人へ)
山上や目路のかぎりのをちこちの河光るなり落日の国 (日向大隅の界にて)
椰子の実を拾ひつ秋の海黒きなぎさに立ちて日にかざし見る (三首都井岬にて)
あはれあれかすかに声す拾ひつる椰子のうつろの流れ実吹けば
日向の国都井の岬の青潮に入りゆく端に独り海見る
黄昏の河を渡るや乗合の牛等鳴き出ぬ黄の山の雲
酔ひ痴れて酒袋如すわがむくろ砂に落ち散り青海を見る
船はてて上れる国は満天の星くづのなかに山匂ひ立つ (日向の油津にて)
山聳ゆ海よこたはるその間に狭しま白し夏の砂原
遊君の紅き袖ふり手をかざしをとこ待つらむ港早や来よ
南国の港のほこり遊君の美なるを見よと帆はさんざめく
大うねり風にさからひ青うゆくそのいただきの白玉の波
大隅の海を走るや乗合の少女が髪のよく匂ふかな
船酔のうら若き母の胸に倚り海をよろこぶやよみどり児よ
落日や白く光りて飛魚のとぶ声しげし秋風の海
港口夜の山そびゆわが船のちひさなるかな沖さして行く
帆柱ぞ寂然としてそらをさす風死せし白昼の海の青さよ
かたかたとかたき音して秋更けし沖の青なみ帆のしたにうつ
風ひたと落ちて真鉄の青空ゆ星ふりそめぬつかれし海に
山かげの闇に吸はれてわが船はみなとに入りぬ汽笛長う鳴る
夕さればいつしか雲は降り来て峯に寝るなり日向高千穂
秋の蝉うちみだれ鳴く夕山の樹蔭に立てば雲のゆく見ゆ
樹間がくれ見居れば阿蘇の青烟はかすかにきえぬ秋の遠空
山鳴に馴れては月の白き夜をやすらに眠る肥の国人よ
ひれ伏して地の底とほき火を見ると人の五つが赤かりし面
麓野の国にすまへる万人を軒に立たせて阿蘇荒るるかな
風さやさや裾野の秋の樹にたちぬ阿蘇の月夜のその大きさや
むらむらと中ぞら掩ふ阿蘇山のけむりのなかの黄なる秋の日
秋のそらうらぶれ雲は霧のごと阿蘇につどひて凪ぎぬる日なり
海の上の空に風吹き陸の上の山に雲居り日は帆のうへに (六首周防灘にて)
やや赤む暮雲を遠き陸の上にながめて秋の海馳するかな
落日のひかり海去り帆をも去りぬ死せしか風はまた眉に来ず
夕雲のひろさいくばくわだつみの黒きを掩ひ日を包み燃ゆ
雲は燃え日は落つ船の旅びとの代赭の面のその沈黙よ
水に棲み夜光る虫は青やかにひかりぬ秋の海匂ふかな
津の国は酒の国なり三夜二夜飲みて更らなる旅つづけなむ
杯を口にふくめば千すぢみな髪も匂ふか身はかろらかに
白雲のかからぬはなし津の国の古塔に望む初秋の山 (四天王寺に登りて)
山行けば青の木草に日は照れり何に悲しむわがこころぞも (箕面山にて)
泣真似の上手なりける小女のさすがなりけり忘られもせず
浪華女に恋すまじいぞ旅人よただ見て通れそのながしめを
われ車に友は柱に一語二語酔語かはして別れ去りにけり (大阪に葩水と別る)
酔うて入り酔うて浪華を出でて行く旅びとに降る初秋の雨
昨日飲みけふ飲み酒に死にもせで白痴笑ひしつつなほ旅路ゆく
住吉は青のはちす葉白の砂秋たちそむる松風の声
秋雨の葛城越えて白雲のただよふもとの紀の国を見る
火事の火の光り宿して夜の雲は赤う明りつ空流れゆく (二首和歌山にて)
町の火事雨雲おほき夜の空にみだれて鷺の啼きかはすかな (紀の国青岸にて)
ちんちろり男ばかりの酒の夜をあれちんちろり鳴きいづるかな
紀の川は海に入るとて千本の松のなかゆくその瑠璃の水
麓には潮ぞさしひく紀三井寺木の間の塔に青し古鐘
一の札所第二の札所紀の国の番の御寺をいざ巡りてむ
粉河寺遍路の衆のうち鳴らす鉦鉦きこゆ秋の樹の間に
鉦鉦のなかにたたずみ旅びとのわれもをころがむ秋の大寺
旅人よ地に臥せ空ゆあふれては秋山河にいま流れ来る (葛城山にて)
鐘おほき古りし町かな折しもあれ旅籠に着きしその黄昏に (二首奈良にて)
鐘断えず麓におこる嫩草の山にわれ立ち白昼の雲見る
雲やゆくわが地やうごく秋真昼鉦も鳴らざる古寺にして (二首法隆寺にて)
秋真昼ふるき御寺にわれ一人立ちぬあゆみぬ何のにほひぞ
みだれ降る大ぞらの星そのもとの山また山の闇を汽車行く (伊賀を越ゆ)
峡出でて汽車海に添ふ初秋の月のひかりのやや青き海 (駿河を過ぐ)
草ふかき富士の裾野をゆく汽車のその食堂の朝の葡萄酒
晩夏の光しづめる東京を先づ停車場に見たる寂しさ
――旅の歌をはり――
舌つづみうてばあめつちゆるぎ出づをかしや瞳はや酔ひしかも
とろとろと琥珀の清水津の国の銘酒白鶴瓶あふれ出づ
灯ともせばむしろみどりに見ゆる水酒と申すを君断えず酌ぐ
くるくると天地めぐるよき顔も白の瓶子も酔ひ舞へる身も
酌とりの玉のやうなる小むすめをかかえて舞はむ青だたみかな
女ども手うちはやして泣上戸泣上戸とぞわれをめぐれる
こは笑止八重山ざくら幾人の女のなかに酔ひ泣く男
あな可愛ゆわれより早く酔ひはてて手枕のまま彼女ねむるなり
睡れるをこのまま盗みわだつみに帆あげてやがて泣く顔を見む
酔ひはててはただ小をんなの帯に咲く緋の大輪の花のみが見ゆ
酔ひはてては世に憎きもの一も無しほとほとわれもまたありやなし
ああ酔ひぬ月が嬰子生む子守唄うたひくれずやこの膝にねむ
君が唄ふ『十三ななつ』君はいつそれになるかや嬰子うむかやよ
渇きはて咽喉は灰めく酔ざめに前髪の子がむく林檎かな
酒の毒しびれわたりしはらわたにあなここちよや沁む秋の風
石ころを蹴り蹴りありく秋の街落日黄なり酔醒めの眼に
もの見れば焼かむとぞおもふもの見れば消なむとぞ思ふ弱き性かな
黒かみはややみどりにも見ゆるかな灯にそがひ泣く秋の夜のひと
立ちもせばやがて地にひく黒髪を白もとゆひに結ひあげもせで
君泣くか相むかひゐて言もなき春の灯かげのもの静けさに
かりそめに病めばただちに死をおもふはかなごこちのうれしき夕 (四首病床にて)
死ぬ死なぬおもひ迫る日われと身にはじめて知りしわが命かな
日の御神氷のごとく冷えはてて空に朽ちむ日また生れ来む
凪く窓押し皐月のそらのうす青を見せよ看護婦胸せまり来ぬ
女ありき、われと共に安房の渚に渡りぬ、あれその傍らにありて夜も昼も断えず歌ふ、明治四十年早春。
恋ふる子等かなしき旅に出づる日の船をかこみて海鳥の啼く
山ねむる山のふもとに海ねむるかなしき春の国を旅ゆく
春や白昼日はうららかに額にさす涙ながして海あふぐ子の
岡を越え真白き春の海辺のみちをはしれりふたつの人車
海哀し山またかなし酔ひ痴れし恋のひとみにあめつちもなし
海死せりいづくともなき遠き音の空にうごきて更けし春の日
ああ接吻海そのままに日は行かず鳥翔ひながら死せ果てよいま
接吻くるわれらがまへにあをあをと海ながれたり神よいづこに
山を見よ山に日は照る海を見よ海に日は照るいざ唇を君
いつとなうわが肩の上にひとの手のかかれるがあり春の海見ゆ
声あげてわれ泣く海の濃みどりの底に声ゆけつれなき耳に
わだつみの白昼のうしほの濃みどりに額うちひたし君恋ひ泣かむ
忍びかに白鳥啼けりあまりにも凪ぎはてし海を怨ずるがごと
君笑めば海はにほへり春の日の八百潮どもはうちひそみつつ
わがこころ海に吸はれぬ海すひぬそのたたかひに瞳は燃ゆるかな
こころまよふ照る日の海へ中ぞらへうれひねむれる君が乳の辺へ
眼をとぢつ君樹によりて海を聴くその遠き音になにのひそむや
砂浜の丘をくだりて松間ゆくひとのうしろを見て涙しぬ
ともすれば君口無しになりたまふ海な眺めそ海にとられむ
君かりにかのわだつみに思はれて言ひよられなばいかにしたまふ
涙もつ瞳つぶらに見はりつつ君かなしきをなほ語るかな
君さらに笑みてものいふ御頬の上にながるる涙そのままにして
このごろの寂しきひとに強ひむとて葡萄の酒をもとめ来にけり
松透きて海見ゆる窓のまひる日にやすらに睡る人の髪吸ふ
闇冷えぬいやがうへにも砂冷えぬ渚に臥して黒き海聴く
闇の夜の浪うちぎはの明るきにうづくまりゐて蒼海を見る
空の日に浸みかも響く青青と海鳴るあはれ青き海鳴る
海を見て世にみなし児のわが性は涙わりなしほほゑみて泣く
白鳥は哀しからずや空の青海のあをにも染まずただよふ
夜半の海汝はよく知るや魂一つここに生きゐて汝が声を聴く
かなしげに星は降るなり恋ふる子等こよひはじめて添寝しにける
ものおほく言はずあちゆきこちらゆきふたりは哀し貝をひろへる
渚ちかく白鳥群れて啼ける日の君がかほより寂しきはなし
浪の寄る真黒き巌にひとり居て春のゆふべの暮れゆくを見る
夕海に鳥啼く闇のかなしきにわれら手とりぬあはれまた啼く
鳥行けりしづかに白き羽のしてゆふべ明るき海のあなたへ
夕やみの磯に火を焚く海にまよふかなしみどもよいざよりて来よ
春の海ほのかにふるふ額伏せて泣く夜のさまの誰が髪に似む
ことあらば消なむとやうにわが前にひたすらわれをうかがふ君よ
君はいまわが思ふままよろこびぬ泣きぬあはれや生くとしもなし
君よ汝が若き生命は眼をとぢてかなしう睡るわが掌に
わがまへに海よこたはり日に光るこのかなしみの何にをののく
海岸の松青き村はうらがなし君にすすめむ葡萄酒の無し
わがうたふかなしき歌やきこえけむゆふべ渚に君も出で来ぬ
くちづけの終りしあとのよこ顔にうちむかふ昼の寂しかりけり
いかなれば恋のはじめに斯くばかり寂しきことをおもひたまへる
伏目して君は海見る夕闇のうす青の香に髪のぬれずや
日は海に落ちゆく君よいかなれば斯くは恋しきいざや祷らむ
白昼さびし木の間に海の光る見て真白き君が額のうれひよ
「木の香にや」「いな海ならむ樹間がくれかすかに浪の寄る音きこうる」
幾千の白羽みだれぬあさ風にみどりの海へ日の大ぞらへ
いづくにか少女泣くらむその眸のうれひ湛えて春の海凪ぐ
海なつかし君等みどりのこのそこにともに来ずやといふに似て凪ぐ
直吸ひに日の光吸ひてまひる日の海の青燃ゆわれに巌にあり
海の声そらにまよへり春の日のその声のなかに白鳥の浮く
海あをし青一しづく日の瞳に点じて春のそら匂はせむ
春のそら白鳥まへり嘴紅しついばみてみよ海のみどりを
燐枝すりぬ海のなぎさに倦み光る昼の日のもと青き魚焼く
春の河うす黄に濁り音もなう潮満つる海の朝凪に入る
暴風雨あとの磯に日は冴ゆなにものに驚かされて犬長う鳴く
白昼の海古びし青き糸のごとたえだえ響く寂しき胸に
月つひに吸はれぬ暁の蒼穹の青きに海の音とほく鳴る
手をとりてわれらは立てり春の日のみどりの海の無限の岸に
春の海のみどりうるみぬあめつちに君が髪の香満ちわたる見ゆ
御ひとみは海にむかへり相むかふわれは夢かも御ひとみを見る
白き鳥ちからなげにも春の日の海をかけれり君よ何おもふ
真昼時青海死にぬ巌かげにちさき貝あり妻をあさり行く
夕ぐれの海の愁ひのしたたりに浸されて瞳は遠き沖見る
蒼ざめし額にせまるわだつみのみどりの針に似たる匂ひよ
海明り天にえ行かず陸に来ず闇のそこひに青うふるへり
ふと袖に見いてし人の落髪を唇にあてつつ朝の海見る
ひもすがら断えなく窓に海ひびく何につかれて君われに倚る
海女の群からすのごときなかにゐて貝を買ふなりわが恋人は
渚なる木の間ゆきゆき摘みためし君とわが手の四五の菜の花
くちつけは永かりしかなあめつちにかへり来てまた黒髪を見る
春の海さして船行く山かげの名もなき港昼の鐘鳴る
――以上――
窓ひとつ朧ろの空へ灯をながす大河沿の春の夜の街
鐘鳴り出づ落日のまへの擾乱のやや沈みゆく街のかたへに
仁和寺の松の木の間をふと思ふうらみつかれし春の夕ぐれ
琴弾くか春ゆくほどにもの言はぬくせつきそめし夕ぐれの人
大空の神よいましがいとし児の二人恋して歌うたふ見よ
君を得ぬいよいよ海の涯なきに白帆を上げぬ何のなみだぞ
あな沈む少女の胸にわれ沈むああ聴けいづく悲しめる笛
みだれ射よ雨降る征矢をえやは射るこの静ごころこの恋ごころ
吹き鳴らせ白銀の笛春ぐもる空裂けむまで君死なむまで
君笑むかああやごとなし君がまへに恋ひ狂ふ子の狂ひ死ぬ見て
山動け海くつがへれ一すぢの君がほつれ毛ゆるがせはせじ
みじろがでわが手にねむれあめつちになにごともなし何の事なし
われら両人相添うて立つ一点に四方のしじまの吸はるるを聴く
思ひ倦みぬ毒の赤花さかづきにしぼりてわれに君せまり来よ
矢継早火の矢つがへてわれを射よ満ちて腐らむわが胸を射よ
生ぬるき恋の文かな筆もろともいざ火に焼かむ炉のむらむら火
胸せまるあな胸せまる君いかにともに死なずや何を驚く
千代八千代棄てたまふなと云ひすててつとわが手枕きはや睡るかな
針のみみそれよりちさき火の色の毒花咲くは誰が唇ぞ
ひたぶるに木枯すさぶ斯る夜を思ひ死なむずわが愚鈍見よ
こよひまた死ぬべきわれかぬれ髪のかげなる眸の満干る海に
いざこの胸千々に刺し貫き穴だらけのそを玩べ春の夜の女
「女なればつつましやかに」「それ憎しなどわれ焼かう火の言葉せぬ」
黒髪に毒あるかをりしとしとにそそぎて侍れ花ちるゆふべ
悲し悲し火をも啖ふと恋ひくるひ斯くやすらかに抱かれむこと
恋ひ狂ひからくも獲ぬる君いだき恍けし顔の驚愕を見よ
とこしへに逃ぐるか恋よとこしへにわれ若うして追はむ汝を
紅梅のつめたきほどを見たまへとはや馴れて君笑みて唇よす
涙さびし夢も見ぬげにやすらかに寝みだれ姿われに添ふ見て
春は来ぬ恋のほこりか君を獲てこの月ごろの悲しきなかに
夕ぐれに音もなうゆらぐさみどりの柳かさびしよく君は泣く
床に馴れ羽おとろへし白鳥のかなしむごとくけふも添寝す
疑ひの野火しめじめと胸を這ふ風死せし夜を消えみ消えずみ
君かりにその黒髪に火の油そそぎてもなほわれを捨てずや
髪を焼けその眸つぶせ斯くてこの胸に泣き来よさらば許さむ
微笑鋭しわれよりさきにこの胸に棲みしありやと添臥しの人
悲しきか君泣け泣くをあざわらひあざわらひつつわれも泣かなむ
燃え燃えて野火いつしかに消え去りぬ黒めるあとの胸の原見よ
さらばよし別るるまでぞなにごとの難きか其処に何のねたまむ
毒の木に火をやれ赤きその炎ちぎりて投げむよく睡る人に
撒きたまへ灰を小砂利をわが胸にその荒るる見て手を拍ちたまへ
手枕よ髪のかをりよ添ひぶしにわかれて春の夜を幾つ寝し
別れ居の三夜は二夜はさこそあれかがなひて見よはや十日経む
思ふまま怨言つらねて彼女がまへに泣きはえ臥さで何を嘲むや
君よなどさは愁れたげの瞳して我がひとみ見るわれに死ねとや
ただ許せふとして君に飽きたらず忌む日もあれどいま斯くてあり
あらら可笑し君といだきて思ふこといふことなきにこの涙はや
毒の香君に焚かせてもろともに死なばや春のかなしき夕
あめつちに乾びて一つわが唇も死して動かず君見ぬ十日
事もなういとしづやかに暮れゆきぬしみじみ人の恋しきゆふべ
かへれかへれ怨じうたがひに倦みもせばいざこの胸へとく帰り来よ
あなあはれ君もいつしか眼盲ひぬわれも盲人の相いだき泣く
この手紙赤き切手をはるにさへこころときめく哀しきゆふべ
さらば君いざや別れむわかれてはまたあひは見じいざさらばさらば
君いかにかかる靜けさ夕ぐれに逝きなば人のいかに幸あらむ
夕ぐれの静寂しとしと降る窓にふと合ひぬ唇のいつまでとなく
恋しなばいつかは斯る憂を見むとおもひし昨のはるかなるかな
わりもなう直よろこびてわが胸にすがり泣く子が髪のやつれよ
心ゆくかぎりをこよひ泣かしめよものな言ひそね君見むも憂し
添臥に馴れしふたりの言も無うかなしむ家に桜咲くなり
「君よ君よわれ若し死なばいづくにか君は行くらむ」手をとりていふ
春哀し君に棄てられはるばると行かばや海のあなたの国へ
知らず知らずわが足鈍る君も鈍る恋の木立の静寂のなかに
怨むまじや性は清水のさらさらに浅かる君をなにうらむべき
恋人よわれらはさびし青ぞらのもとに涯なう野の燃ゆるさま
われ歌をうたへりけふも故わかぬかなしみどもにうち追はれつつ
みな人にそむきてひとりわれゆかむわが悲しみはひとにゆるさじ
君見ませ泣きそぼたれて春の夜の更けゆくさまを真黒き樹樹を
雪暗うわが家つつみぬ赤赤と炭燃ゆる夜の君が髪の香
然なり先づ春消えのこる松が枝の白の深雪の君とたたへむ
君来ずばこがれてこよひわれ死なむ明日は明後日は誰知らむ日ぞ
泣きながら死にて去にけりおん胸に顔うづめつつ怨みゐし子は
おもひみよ青海なせるさびしさにつつまれゐつつ恋ひ燃ゆる身を
戸な引きそ戸の面は今しゆく春のかなしさ満てり来よ何か泣く
狂ひつつ泣くと寝ざめのしめやけき涙いづれが君は悲しき
鳥は籠君は柱にしめやかに夕日を浴びぬなど啼かぬ鳥
煙たつ野ずえの空へ野樹いまだ芽ふかぬ春のうるめるそらへ
はらはらに桜みだれて散り散れり見ゐつつ何のおもひ湧かぬ日
蛙鳴く耳をたつればみんなみにいなまた西に雲白き昼
朱の色の大鳥あまた浮きいでよいま晩春の日は空に饐ゆ
あな寂し縛められて黙然と立てる巨人の石彫まばや
つかれぬる胸に照り来てほのかをるゆく春ごろの日のにほひかな
田のはづれ林のうへのゆく春の雲の静けさ蛙鳴くなり
汪洋と濁れる河のひたながれ流るるを見て眼をひらき得ず
酔ひはてぬわれと若さにわが恋にこころなにぞも然かは悲しむ
聳やげる皐月のそらの樹の梢に幾すぢ青の糸ひくか風
わくら葉か青きが落ちぬ水無月の死しぬる白昼の高樫の樹ゆ
鷺ぞ啼く皐月の朝の浅みどり揺れもせなくや鷺空に啼く
水ゆけり水のみぎはの竹なかに白鷺啼けり見そなはせ神
いと幽けく濃青の白日の高ぞらに鳶啼くきこゆ死にゆくか地
一すぢの糸の白雪富士の嶺に残るが哀し水無月の天
風わたる見よはつ夏のあを空を青葉がうへをやよ恋人よ
山を見き君よ添寝の夢のうちに寂しかりけり見も知らぬ山
人棲まで樹樹のみ生ひしかみつ代のみどり照らせし日か天をゆく
われ驚くかすかにふるふわだつみの青き眺めわが脈搏に
掟てられて人てふものの為すべきをなしつつあるに何のもだえぞ
地のうへに生けるものみな死にはてよわれただ一人日を仰ぎ見む
われ敢て手もうごかさず寂然とよこたはりゐむ燃えよ悲しみ
われ死なばねがはくはあとに一点のかげもとどめで日にいたりてむ
雲見れば雲に木見れば木に草にあな悲しみのかげ燃えわたる
わが胸の底の悲しみ誰知らむただ高笑ひ空なるを聞け
むしろわれけものをねがふ思ふまま地の上這ひ得るちからをねがふ
かなしみは死にゆきただち神にゆきただひとすぢに久遠に走る
あれ行くよ何の悲しみ何の悔い犬にあるべき尾をふりて行く
天の日に向ひて立つにたへがたしいつはりにのみ満ちみてる胸
山の白昼われをめぐれる秋の樹の不断の風に海の青憶ふ
月光の青のうしほのなかに浮きいや遠ざかり白鷺の啼く
月の夜や君つつましうねてさめず戸の面の木立風真白なり
十五夜の月は生絹の被衣して男をみなの寝し国をゆく
白昼のごと戸の面は月の明う照るここは灯の国君とぬるなり
君睡れば灯の照るかぎりしづやかに夜は匂ふなりたちばなの花
寝すがたはねたし起こすもまたつらしとつおいつして虫を聴くかな
ふと虫の鳴く音たゆれば驚きて君見る君は美しう睡る
君ぬるや枕のうへに摘まれ来し秋の花ぞと灯は匂やかに
美しうねむれる人にむかひゐてふと夜ぞかなし戸に月や見む
真昼日のひかりのなかに燃えさかる炎か哀しわが若さ燃ゆ
狂ひ鳥はてなき青の大空に狂へるを見よくるへる女
玉ひかる純白の小鳥たえだえに胸に羽うつ寂しき真昼
秋の風木立にすさぶ木のなかの家の灯かげにわが脈はうつ
つとわれら黙しぬ灯かげ黒かみのみどりは匂ふ風過ぎて行く
われらややに頭をたれぬ胸二つ何をか思ふ夜風遠く吹く
風消えぬ吾もほほゑみぬ小夜の風聴きゐし君のほほゑむを見て
つと過ぎぬすぎて声なし夜の風いまか静かに木の葉ちるらむ
風落ちぬつかれて樹樹の凪ぎしづむ夜を見よ少女さびしからずや
風凪ぎぬ松と落葉の木の叢のなかなるわが家いざ君よ寝む
下巻 自明治四十一年四月 至同四十三年一月
いざ行かむ行きてまだ見ぬ山を見むこのさびしさに君は耐ふるや
いづくよりいづくへ行くや大空の白雲のごと逝きし君はも (三首独歩氏を悼む)
仰ぎみる御そら庭の樹あめつちの冷かなりや君はゐまさず
君ゆけばむらがりたちて静けさの尽くるを知らず君追ふとおもふ
みんなみの軒端のそらに日輪の日ぼとかよふを見て君と住む
おのづから熟みて木の実も地に落ちぬ恋のきはみにいつか来にけむ
女あり石に油をそそぎては石焼かむとす見るがさびしき
いざ行かむ行衛は知らぬとどまらばかなしかりなむいざ君よ夙く
若ければわれらは哀し泣きぬれてけふもうたふよ恋ひ恋ふる歌
うらかなしこがれて逢ひに来しものを驚きもせでひとのほほゑむ
悲しまず泣かずわらはぬ昼夜に馴れしかいまはさびしくもなし
うちしのび夜汽車の隅にわれ座しぬかたへに添ひてひとのさしぐむ (以下或る時に)
野のおくの夜の停車場を出でしときつとこそ接吻をかはしてしかな
摘みてはすて摘みてはすてし野のはなの我等があとにとほく続きぬ
山はいま遅き桜のちるころをわれら手とりて木の間あゆめり
鬢の毛に散りしさくらのかかるあり木のかげ去らぬゆふぐれのひと
木の芽摘みて豆腐の料理君のしぬわびしかりにし山の宿かな
春の日の満てる木の間にうち立たすおそろしきまでひとの美し
小鳥よりさらに身かろくうつくしく哀しく春の木の間ゆく君
静かなる木の間にともに入りしときこころしきりに君を憎めり
君すててわれただひとり木の間より岡にいづれば春の雲見ゆ
山の家の障子細目にひらきつつ山見るひとをかなしくぞ見し
ゆく春の山に明う雨かぜのみだるるを見てさびしむひとよ
狭みどりのうすき衣をうち着せむくちづけはてて夢見るひとに (以上)
古寺の木立のなかの離れ家に棲みて夜ごとに君を待ちにき
ものごしに静けさいたく見えまさるひとと棲みつつはつ夏に入る
樹樹の間に白雲見ゆる梅雨晴の照る日の庭に妻は花植う
くちつけをいなめる人はややとほくはなれて窓に初夏の雲見る
わが妻はつひにうるはし夏たてば白き衣きてやや痩せてけり
香炉ささげ初夏の日のわらはたち御そらあゆめり日の静かなる
はつ夏の雲あをそらのをちかたに湧きいづる昼麦の笛吹く
燐枝すりぬ赤き毛虫を焼かむとてただ何となくくるしきゆふべ
とこしへに解けぬひとつの不可思議の生きてうごくと自らをおもふ
はたた神遠鳴りひびき雨降らぬ赤きゆふべをひとり酒煮る
夕されば風吹きいでぬ闇のうちの樹梢見ゐつつまたおもひつぐ
夕やみのややに明るみ大ぞらに月のかかればやや思ひ凪ぐ
ひとりなればこのもちつきの夏の夜のすずしきよひをいざひとり寝む
八月の初め信州軽井沢に遊びぬ、その頃詠める歌三十首。
火を噴けば浅間の山は樹を生まず茫として立つ青天地に
天地の静寂わが身にひたせまるふもと野に居て山の火を見る
八月や浅間が岳の山すそのその荒原にとこなつの咲く
麓なる山のひとつのいただきの青深草に寝て浅間見る
夢も見ず旅寝かさねぬ火の山の裾の月夜の白き幾夜を
火の山の裾の松原月かげの疎き月夜をほととぎす啼く
火の山やふもとの国に白雲の居る夜のそらの一すぢの煙
大ぞらに星のふる夜を火の山の裾に旅寝し妻をしぞ思ふ
夜となればそらを掩ひて高く見ゆ白昼は低しけむり噴く山
火の山にしばし煙の断えにけりいのち死ぬべくひとのこひしき
女ありみやこにわれを待つときく静かなりけり山の火を見る
月見草見ゐつつ居ればわかれ来し妻が物思ふすがたしぬばゆ
黒髪のそのひとすぢのこひしさの胸にながれて尽きむともせず
わかれ来て幾夜経ぬると指折れば十指に足らず夜のながきかな
ゆるしたまへ別れて遠くなるままにわりなきままにうたがひもする
青草のなかにまぢりて月見草ひともと咲くをあはれみて摘む
あめつちにわが跫音のみ満ちわたる夕の野なり月見草摘む
ものをおもふ四方の山べの朝ゆふに雲を見れどもなぐさみもせず
紅滴る桃の実かみて山すその林ゆきつつ火の山を見る
虫に似て高原はしる汽車のありそらに雲見ゆ八月の昼
白雲のいざよふ秋の峯をあふぐちひさなるかな旅人どもは
糸のごとくそらを流るる杜鵑あり声にむかひて涙とどまらず
うつろなる命をいだき真昼野にわが身うごめき杜鵑聴く
ほととぎす聴きつつ立てば一滴のつゆより寂しわが生くが見ゆ
わかれては十日ありえずあわただしまた碓氷越え君見むと行く
胸にただ別れ来しひとしのばせてゆふべの山をひとり越ゆなり
瞰下ろせば霧に沈めるふもと野の国のいづくぞほととぎす啼く
身じろがずしばしがほどを見かはせり旅のをとこと山の小蛇と
秋かぜや碓氷のふもと荒れ寂し坂本の宿の糸繰の唄 (坂本に宿りて)
まひる野の光のなかに白雲はうづまきてありふもと国原 (妙義山にて)
旅びとはふるきみやこの月の夜の寺の木の間を飽かずさまよふ (三首奈良にて)
はたご屋へ杜の木の間の月の夜の風のあはれに濡れてかへりぬ
伏しをがみふしをがみつつ階のゆふべのやみにきえよとぞおもふ
大いなるうねりに船の載れるとき甲板にゐて君をおもひぬ (播磨灘にて)
恋人のうまれしといふ安芸の国の山の夕日を見て海を過ぐ (瀬戸にて)
とき折りに淫唄うたふ八月の燃ゆる浜ゆき燃ゆる海見て (五首故郷にて)
峰あまた横ほり伏せる峡間の河越えむとし蜩を聴く
父の髪母の髪みな白み来ぬ子はまた遠く旅をおもへる
雲去ればもののかげなくうす赤き夕日の山に秋風ぞ吹く
星くづのみだれしなかにおほどかにわが帆柱のうち揺ぐ見ゆ
蓄音機ふとしも船の一室に起るがきこゆ海かなしけれ
なにものに欺かれ来しやこの日ごろ口惜し腹立つたし秋風を聴く
秋立てどよそよそしくもなりにけり風は吹けども葉は落つれども
とも思いひかくもおもへどとにかくにおもひさだめて幸祝せむ
いねもせで明かせる朝の秋かぜの声にまぢりてすずめ子の啼く
うらさびし尽きなく行くける大河のほとりにゆきて泣かむとぞおもふ
闇うれしこよひ籬根のこほろぎの身にしむままに出でて聴くかな
霧ふけばけふはいつより暮はやきゆふべなりけりこほろぎの鳴く
時として涙をおぼゆ草木の悠悠として日を浴ぶる見て
消えやらぬ大あめつちの生物のひとつのわれに秋かぜぞ吹く
君がすむ恋の国辺とわが住むめる国のさかひの一すぢの河
白粉と髪のにほひをききわけむ静かなる夜の黄色なるともしび
夕ぐれの街をし行けばそそくさと行きかふ人に眼も鼻も無し
わが胸に旅のをとこの情なしのこころやどりてそそのかすらく
物おもへばこの茫漠のあめつちにわれただ独り生くとさびしき
秋たてば街のはづれの楢の木の木立に行きてよくものをおもふ
わがこころ行くにまかせてゆかしめよ世にこれよりのなぐさめは無し
蝋燭の火の穂赤きをつくづくと見つめゐてふと秋風をきく
めぐりあひしづかに見守りなみだしぬわれとわれとのこころとこころ
秋晴のまちに逢ひぬる乞食の爺の眸見て旅をおもひぬ
牛に似てものもおもはず茫然と家を出づれば秋かぜの吹く
野菊ぞとさも媚びなよるすがたして野に咲く見れば行きもかねつる
湯槽より窓のガラスにうつりたる秋風のなかの午後の日を見る
落初めの桐のひと葉のあをあをとひろきがうへを夕風のゆく
人の声車のひびき満ちわたるゆふべの街に落葉するなり
秋かぜは空をわたれりゆく水はたゆみもあらず葦刈る少女
足とめて聴けばかよひ来河むかひ枯葦のなかの葦刈の唄
魚釣るや晩取河のながれ去り流れさる見つつ餌は取られがち
わだの原生れてやがて消えてゆく浪のあをきに秋かぜぞ吹く
相むかひ世に消えがたきかなしみの秋のゆふべの海とわれとあり
ゆふぐれの沖には風の行くあらむ屍のごとく松にもたるる
音もなくゆふべの海のをちかたの闇のなかゆく白き波見ゆ
行き行きて飽きなば旅にしづやかにかへりみもなく死なむとぞおもふ
ひたすらに君に恋しぬ白菊も紅葉も秋はもののさびしく
病みぬれば世のはかなさをとりあつめ追はるるがごと歌につづりぬ
あれ見たまへkのもかのもの物かげをしのびしのびに秋かぜのゆく
少女子のむねのちひさきかなしみに溺れてわれは死にはててけり
君見れば獣のごとくさいなみぬこのかなしさをやるところなみ
なほ飽かずいやなほあかず苛みぬ思ふままなるこの女ゆゑ
長椅子にいねて初冬午後の日を浴ぶるに似たる恋づかれかな
なにものに追はれ引かれて斯く走るをもしろきこと世に一もなし
この林檎つゆしたたらばありし日のなみだに似むとわかき言いふ
あはれそのをみなの肌しらずして恋のあはれに泣きぬれし日よ
あはれ神ただあるがままわれをしてあらしめたまへ他にいのる無し
かかる時声はりあげてかなしさを歌ふ癖ありきそれも止みつる
わが住むは寺の裏部屋庭もせに白菊さけり身に来よ女
消えもせず恋の国より追はれ来し身にうつり香のあはくかなしく
見かへるな恋の世界のたふとさは揺れずしづかに遠ざかりゆく
世に最もあさはかなればとりわけて女の泣くをあはれとぞおもふ
黒牛の大いなる面とむかひあひあるがごとくに生くにつかれぬ
ほこり湧く落日の街をひた走る電車のすみのひとりの少女
仰ぎみてこころぞながる街の樹の落日のそらにおち葉するあり
われうまれて初めてけふぞ冬を知る落葉のこころなつかしきかな
落ちし葉のひと葉のつぎにまた落ちむ黄なる一葉の待たるるゆふべ
あめつちの静かなる時そよろそよろ落葉をわたるゆふぐれの風
早やゆくかしみじみ汝にうちむかふひまもなかりきさらばさらば秋
忍び来てしのびて去にぬかの秋は盲目なりけりものいはずけり
大河のうへをながるる一葉のおち葉のごとしものもおもはず
わが妻よわがさびしさは青のいろ君がもてるは黄朽葉ならむ
めぐりあひふと見交して別れけり落葉林のをとこと男 (戸山が原にて)
冬木立落葉のうへに昼寝してふと見しゆめのあはれなりしかな
武蔵野は落葉の声に明け暮れぬ雲を帯びたる日はそらを行く
ゆふまぐれ落葉のなかに見いてつる松かさの実を手にのせてみぬ
かすかなる胸さわぎあり燃え燃えぬ黄葉ふりしきる冬がれの森
いかにせむ胸の落葉の落ちそめてあるがごときをおもひ消しえず
ふりはらひふりはらひつつ行くが見ゆ落葉がくれをひとりの男
いと静かにものをぞおもふ山白き十二月こそゆかしかりけれ
梢より葉のちるごとくものおもひありとしもなきにむねのかなしき
うす赤く木枯すさぶ落日の街のほこりのなかにおもはく
窓あくればおもはぬそらにしらじらと富士見ゆる家に女すまひき
日向ぼこ側にねむれる犬の背を撫でつつあればさびしうなりぬ
近きわたり寺やたづねてめぐらなむ女を棄ててややさびしかり
別るる日君もかたらずわれ云はず雪ふる午後の停車場にあり
別るとて停車場あゆむうつむきのひとの片手にヴィオロンの見ゆ
別れけり残るひとりは停車場の群集のなかに口笛をふく
大鳥の空を行くごとさやりなき恋するひとも斯くや嘆かむ
男といふ世に大いなるおごそかのほこりに如かむかなしみありや
ほのかにもおもひは痛しうす青の一月のそらに梅つぼみ来ぬ
うきことの限りも知らずふりつもるこのわかき日をいざや歌はむ
清ければ若くしあればわがこころそらへ去なむとけふもかなしむ
ゆめのごとくありのすさびの恋もしきよりどころなくさびしかりしゆゑ
枯れしのち最もあはれ深かるは何花ならむなつかしきかな
男なれば歳二十五のわかければあるほどのうれひみな来よとおもふ
獣の病めるがごとくしづやかに運命のあとに従ひて行く
爪延びぬ髪も延び来ぬやすみなく人にまぢりてわれも生くなり
狂ひ鳥日を追へるよりあはれなり行衛も知らずひとの迷へる
あさましき歌のみおほくなりにけりものの終りのさびしきなかに
一月より二月にかけ安房の渚に在りき、その頃の歌六十九首。
ふね待ちつ待合室の雑音に海をながめて巻たばこ吹く
おもひ屈し古ぼろ船に魚買の群とまぢりて房州へ行く
物ありて追はるるごとく一人の男きたりぬ海のほとりに
病院の玻璃戸に倚れば海こえておぼろ夜伊豆の山焼くる見ゆ
まつ風の明るき声のなかにして女をおもひ青海を見る
なにほどのことにやあらむ夜もいねで海のほとりに人の嘆くは
海に来ぬ思ひあぐみてよるべなき身はいづくにも捨てどころなく
われひとり多く語りてかへり来ぬ月照る松のなかの家より
ともすれば喀くに馴れぬる血なればとこともなげにも言ひたまふかな
うす青くけふもねがての枕べに這ひまつはれり海のひびきは
藻草焚く青きけむりを透きて見ゆ裸体の海女と暮れゆく海と
われよりもいささか高きわか松の木かげに立ちて君をおもへり
朝起きて煙草しづかにくゆらせるしばしがほどはなにも思はず
日は日なりわがさびしさはわがのなり白昼なぎさの砂山に立つ
ここよりは海も見えざる砂山のかげの日向にものをおもひぬ
いづかたに行くべきわれはここに在りこころ落ち居よわれよ不安よ
風落ちて渚木立に満ちわたる海のひびきの白昼のかなしみ
きさらぎや海にうかびてけむりふく寂しき島のうす霞みせり
火の山にのぼるけむりにむかひゐてけふもさびしきひねもすなりき
大島の山のけむりのいつもいつも断えずさびしきわがこころかな
晴れわたる大ぞらのもと火の山のけむりはけふも白白とたつ
夕やみに白帆を下す大船の港入りこそややかなしけれ
けふは早や恋のほかなるかなしみに泣くべき身ともなりそめしかな
少年のゆめのころもはぬがれたりまこと男のかなしみに入る
あはれこころ荒みぬればか眼も見えず海を見れども日を仰げども
人見れば忽ちうすき皮を着るわが性ゆゑの尽きぬさびしさ
天地に享けしわが性やうやうに露はになり来海に来ぬれば
つひにわれ薬に飽きぬ酒こひし身も世もあらず飲みて飲み死なむ
やまひには酒こそ一の毒といふその酒ばかり恋しきは無し
あさましく酒をたふべて荒浜に泣き狂へども笑ふ人もなし
愚かなり阿呆烏の啼くよりもわがかなしみをひとに語るは
あめつちにわが残し行くあしあとのひとつづつぞと歌を寂びしむ
わがこころ濁りて重きゆふぶれは軒のそとにも行くを好まず
けふもまた変ることなきあら海の渚を同じわれがあゆめり
安房の国海にうかびて冬知らず紅梅白梅いまさかりなり
けふ見ればひとがするゆゑわれもせしをかしくもなき恋なりしかな
海に行かばなぐさむべしとひた思ひこがれし海に来は来つれども
耳もなく目なく口なく手足無きあやしきものとなりはてにけり
眼覚めつるその一瞬にあたらしき寂しきわれぞふと見えにける
心より歌ふならねばいたづらに声のみまよふ宵をかなしむ
海あをくあまたの山等横伏せりわが泣くところいまだ尽くる無し
やどかりの殻の如くに生くかぎりわれかなしみをえは捨てざらむ
なつかしく静かなるかな海の辺の松かげの墓にけふも来りぬ
このごろは夜半にぞ月のいづるなりいねがての夜もよくつづくかな
いつ知らず生れし風の月の夜の明けがたちかく吹くあはれなり
物かげに息をひそめて大風の海に落ちゆく太陽を見る
蜑が家に旅寝かさねてうす赤き榾の火かげに何をおもふか
白白とかがやける浪ひかる砂白昼のなぎさに巻煙草吸ふ
いたづらにものを思ふとくせづきてけふもさびしく渚をまよふ
青海の鳥の啼くよりいや清くいやかなしきはいづれなるらむ
これもまたあざむきならむいざ行かむ清きあなたへ海のさそへど
砂山の起き臥ししげきあら浜のひろきに出でて白昼の海聴く
わがほどのちひさきもののかなしみの消えむともせず天地にあり
好かざりし梅の白きをすきそめぬわが二十五歳の春のさびしさ
をぼろおぼろ海の凪げる日海こえてかなしきそらに白富士の見ゆ
海のあなたおぼろに富士のかすむ日は胸のいたみのつぬに増しにき
安房の国の朝のなぎさのさざなみの音のかなしさや遠き富士見ゆ
うちよせし浪のかたちの砂の上に残れるあとをゆうふべさまよふ
思ひ倦めば昼もねむりて夢を見きなつかしかりき海辺の木立
おぼろ夜や水田のなかの一すぢの道をざわめき我等は海へ
おぼろ夜のこれは夢かも渚にはちひさき音の断えずまろべる
おぼろ夜の多人数なりしそがなかのつかね髪なりしひとを忘れず
日は黄なり灘のうねりの濁れる日敗残者はまた海に浮く
男なり為すべきことはなしはてむけふもこの語に生きすがりぬる
鳥が啼く濁れるそらに鳥が啼く別れて船の甲板に在り
わかれ来て船の碇のくさり綱錆びしがうへに腰かけて居り (以上)
このままに無口者となりはてむ云ふべきことはみな腹立たし
おのづからこころはひがみ眼もひがみ暗きかたのみもとめむとする
角もなく眼なき数十の黒牛にまぢりて行くかばややなぐさまむ
鉛なすおもきこころにゆふぐれの闇のふるよりかなしきは無し
ただ一つ黒きむくろぞ眼には見ゆおもひ尽きては他にものもなし
恋といふうるはしき名にみづからを欺くことにややつかれ来ぬ
いふがごと恋に狂へる身なりしがこころたえせずさびしかりしは
おほぞらのたそがれのかげにさそはれて涙あやふくなりそめしかな
なにごともこころひとつにおさめおきてひそかに泣くに如くことは無し
あはれまたわれうち棄ててわがこころひとのなさけによりゆかむとす
恋もしき歌もうたひきよるべなきわが生命をば欺かむとて
かりそめの己がなさけに神かけていのちささぐる見ればあはれなり
つゆほども酔ふこと知らぬうるはしき女をけふももてあそべども
いかにして欺くは恋ひにし狂ひにし不思議なりきとさびしく笑ふ
わがいのち安かりしかなひとが泣きひとが笑ふにうち混りゐて
心いよよ独りをおもふ身にしみていよいよひとのなさけしげきまま
よるべなき生命生命のさびしさの満てる世界にわれも生くなり
うちたえて人の跫音の無かるべき国のあらじや行きて死なまし
斯くつねに胸のさわがばひろめ屋の太鼓うちにもならましものを
行くところとざまかうざま乱れたるわかきいのちに悔を知らすな
酒飲まば女いだかば足りぬべきそのさびしさかそのさびしさか
沈丁花みだれて咲ける森にゆきわが恋人は死になむといふ
大天地みどりさびしくひそまりぬ若き男のしづかに愁へる
汚れせずわかき男のただひとりこのあめつちをいかに歩まむ
青わだつみ遠くうしほのひびくより深しするどし男のうれへる
水いろのうれひに満てる世界なりいまわがおもひほしいままなる
降ると見えずしづかに青き雨ぞふるかなしみつかれ男ねむれる
ニコライの大釣鐘の鳴りいでて夕さりくればつねにたづねき
酒飲まじ煙草吸はじとひとすぢに妻をいだきに友のがれたり
消息もたえてひさしき落魄の男をいまだ覚えたまふや
あらためてまことの恋をとめ行かむ来しかたあまりさびしかりしか
恋なりししからざりしか知らねどもうきことしげきゆめなりしかな
いざ行かむいづれ迷ひは死ぬるまでさめざらましをなにかへりみむ
帰らずばかへらぬままに行かしめよ旅に死ねよとやりぬこころを
安房の国海のなぎさの松かげに病みたまふぞとけふもおもひぬ
海に沿ふ松の木の間の一すぢのみちを独りしけふも歩むか
君が住む海のほとりの松原の松にもたれて歌うたはまし
山ざくら咲きそめしとや君が病む安房の海辺の松の木の間に
きはみなき青わだなかにさまよへる海のひびきかわれは生くなり
思ひうみ断えみ断えざみわがいのち夜半にぞ風の流るるを聴く
真昼日の小野の落葉の木の間ゆきあるかなきかの春にかなしむ
春は来ぬ落葉のままにしづかなる木立がくれをそよ風のふく
憫れまれあはれむといふあさましき恋の終りに近づきしかな
かなしきはつゆ掩ふなくみぢからをうちさらしつつなほ恋ひわたる
はや夙くもこころ覚めゐし女かとおもひ及ぶ日死もなぐさまず
女なればあはれなればと甲斐もなくくやしくもげに許し来つるかな
憫れぞとおもひいたれば何はおき先づたへがたく恋しきものを
逃れゆく女を追へる大たわけわれぞと知りて眼眩むごとし
斯くてなほ女をかばふ反逆のこころが胸にひそむといふは
なにか泣くみづからもわれを欺きし恋ならぬかは清く別れよ
唯だ彼女が男のむねのかなしみを解し得で去るをあはれにおもふ
林なる鳥と鳥とのわかれよりいやはかなくも無事なりしかな
千度び恋ひ千度びわかれてかの女けだしや泣きしこと無かるらむ
別れゆきふりもかへらぬそのうしろ見居つつ呼ばず泣かずたたずむ
鼻のしたながきをほこる汝とて欺くは清くも棄てられつるか
別るとて冷えまさりゆく女にはわが泣くつらのいかにうつれる
山奥にひとり獣の死ぬるよりさびしからずや恋の終りは
やみがたき憤りより棄てむとす男のまへに泣くな甲斐無く
かへりみてしのぶよすがにだもならぬ斯る別れをいつか思ひし
報いなき恋に甘んじ飽く知らず汝をおもふと誰か言はむや
あさましく甲斐なく怨み狂へるは命を蛇に吸はるるに似る
鳥去りてしろき波寄るゆふぐれの沖のいはほか恋にわかれき
海のごとく男ごころ満たすかなしさを静かに見やり歩み去りし子
別れといふそれよりもいや耐へがたしすさみし我をいかに救はむ
恋ひに恋ひうつつなかりしそのかみに寧ろわかれてあるべかりしを
わがこころ女え知らず彼女が持つあさきこころはわれ掬みもせず
再びは見じとさけびしくちびるの乾むとする時のさびしさ
柱のみ残れる寺の壊跡にまよふよりげにけふはさびしき
いつまでを待ちなばありし日のごとく胸に泣き伏し詫ぶる子を見む
詫びて来よ詫びて来よとぞむなしくも待つくるしさに男死ぬべき
別れてののちの互いを思ふこと無かるべきなり固く誓はむ
ふとしては何も思はずいとあさきかりそめごとに別れむとおもふ
斯くばかりくるしきものをなにゆゑに泣きて詫びしを許さざりけむ
おもひやるわが生のはてのいやはてのゆふべまでをか独りなるらむ
やうやうにこころもしづみ別れての後のあはれを味はむとす
灯赤き酒のまどゐもをはりけりさびしき床に寝にかへるべし
冷笑すいのち死ぬべくここちよく涙ながしてわれ冷笑す
死ぬばかりかなしき歌をうたはましよりどころなく身のなりてきぬ
これはこのわが泣けるにはあらざらむあらめづらしや涙ながるる
とりとめてなにかかなしき知らねどもとすればなみだ頬をながるる
わがめぐりいづれさびしくよるべなきわかきいのちが数さまよへり
さびしきはさびしきかたへさまよへりこのあはれさの耐へがたきかな
花つみに行くがごとくにいでゆきてやがて涙にぬれてかへりう来ぬ
櫛とればこころいささか晴るるとてさびしや人のけふも髪をゆふ
富士見えき海のあなたに春の日の安房の渚にわれら立てりき
おぼろなる春の月の夜落葉のかげのごとくもわれのあゆめり
まどかけをひきて寝ぬれば春の夜の月はかなしく窓にさまよふ
首たかくあげては春のそらあふぎかなしげに啼く一羽の鵝鳥
街なかの堀の小橋を過ぎむとしふと春の夜の風に逢ひぬる
春の昼街をながしの三味がゆく二階の窓の黄なるまどかけ
彼はよく妻ののろけをいふ男まことやすこし眼尻さがりたる
春のそらそれとも見えぬ太陽のかげのほとりのうす雲のむれ
ひややかに梢に咲き満ちしらしらと朝づけるほどの山ざくら花
咲き満てる桜のなかのひとひらの花の落つるをしみじみと見る
かなしめる桜の声のきこゆなり咲き満てる大樹白昼風もなし
寝ざめゐて夜半に桜の散るをきく枕のうへのさびしきいのち
海なかにうごける青の一点を眼にとこしへに死せしむるなかれ
よるべなみまた懲りずまに萌えそめぬあはれやさびしこのこひごころ
よるべなき生命生命が対ひ居のあはれよるべなき恋に落ちむとす
はかなかりし恋のうちなるおもひでのすくなき数を飽かずかぞふる
かへるべき時し来ぬるかうらやすしなつかしき地へいざかへらなむ
知らざりきわが眼のまへに死といふなつかしき母のとく待てりしを
をさな子のごとくひたすら流涕すふと死になむと思ひいたりて
海の辺に行きて立てどもなぐさまず死をおもへどもなほなぐさまず
まことなり忘れゐたりきいざゆかむ思ふことなしに天のあなたへ
根の知れぬかなしさありてなつかしくこころをひくに死にもかねたる
死をおもへば梢はなれし落葉の地にゆくよりなつかしきかな
ゆふ海の帆の上に消えしそよ風のごとくにこの世去なとむぞおもふ
追はるるごと驚くひまもあらなくに別れきつひに見ざるふたりは
若うして傷のみしげきいのちなり蹌踉としてけふもあゆめる
然れども時を経ゆかばいつ知らずこのかなしさをまた忘るべし
ふたたびはかへり来ることあらざらむさなりいかでかまたかへり来む
ほのかなるさびしさありて身をめぐるかなしみのはてにいまか来にけむ
思ふまま涙ながせしゆふぐれの室のひとりは石にかも似む
死に隣る恋のきはみのかなしみの一すぢみちを歩み来しかな
故わかずわれら別れてむきむきにさびしきかたにまよひ入りぬる
見るかぎり友の顔みな死にはてしさびしきなかに独りものをおもふ
おぼろ夜の停車場内の雑沓に一すぢまぢる少女の香あり
疲れはてて窓をひらけばおぼろ夜の嵐のなかになく蛙あり
ゆく春の軒端に見ゆるゆふぞらの青のにごりに風のうごけり
ちやるめらの遠音や室にちらばれる密柑の皮の香を吐くゆふべ
うしなひし夢をさがしにかへりゆく若きいのちのそのうしろかげ
わが生命よみがへり来ぬさびしさにわかくさのごとくうちふるへつつ
わが行くは海のなぎさの一すぢの白きみちなり尽くるを知らず
玻璃戸漏り暮春の月の黄に匂ふ室に疲れてかへり来しかな
ガラス戸にゆく春の風をききながら独り床敷きともしびを消す
四月すゑ風みだれ吹くこよひなりみだれてひとのこひしき夜なり
あめつちのみどり濃き日となりぬ我等きそうてかなしみにゆく
また見じと思ひさだめつさりげなく静かにひとを見て別れ来ぬ
真昼の日そらに白みぬ春暮れて夏たちそむる嵐のなかに
たた一歩踏みもたがへて西ひがしわが生のかぎりとほく別れぬ
うす濁る地平のはての青に見ゆかすかに夏のとどろける雲
めぐりあひやがてただちに別れけり雨ふる四月すゑの九日
ゆく春の嵐のみだれ雨のみだれしづかにひとと別るる日なり
かなしみの歩みゆく音のかすかなり疲れし胸をとほくめぐりて
しめやかに嵐みだるるはつ夏の夜のあはれを寝ざめながむる
夏を迎ふおもひみだれてかき濁りつかれしむねは歌もうたはず
旅人あり街の辻なる煉瓦屋の根に行き倒れ死にはてにける
いつしかに春は暮れけりこころまたさびしきままにはつ夏に入る
空のあなた深きみどりのそこひよりさびしき時にかよふひびきあり
あをあをと若葉萌えいづる森なかに一もと松の花咲きにけり
そこ知らず思ひ沈みて真昼時一樹の青のたかきにむかふ
大木の幹に片へのましろきにこぼれぬる日の夏のかなしみ
窓ちかき水田のなかの榛の木の日にげに青み嵐するなり
大木の青葉のなかに小鳥啼く細かに昼の日をみだしつつ
とりみだし哀しみさけび讃嘆すああ天地に夏の来れる
生くといふ否むべからぬちからより逃れて恋にすがらむとしき
ひややかにことは終りき別れてき斯くあるわれをつくづくと見る
思ひいでてなみだはじめて頬をつたふ極り知らぬわかれなりしかな
女ひとり棄てしばかりの驚きに眼覚めてわれのさびしさを知る
甲斐もなくしのびしのびにいや深にひとに恋ひつつ衰へにけり
忽然と息断えしごとく夜ふかく寝ざめてひとをおもひいでしかな
怨むまじやなにかうらみむ胸のうちのかなしきこころ斯くちかひける
ありし夜のひとの枕に敷きたりしこのかひなかも斯く痩せにける
わが恋の終りゆくころとりどりに初なつの花の咲きいでにけり
音もなく人等死にゆく音もなく大あめつちに夏は来にけり
海山のよこたはるごとくおごそかにわが生くとふを信ぜしめたまへ
きはみなき生命のなかのしばらくのこのさびしさw感謝しまつる
あなさびし白昼を酒に酔ひ痴れて皐月大野の麦畑をゆく
青草によこたはりゐてあめつちにひとりなるものの自由をおもふ
畑なかにふと見いでつる痩馬の草食みゐたり水無月真昼
ひややかにつひに真白き夏花のわれ等がなかにあり終りけり
棕梠の樹の黄色の花のかげに立ち初夏の野をとほくながむる
初夏の野ずゑの川の濁れるにものの屍の浮きしづみ行く
けだものはその死処とこしへにひとに見せずと聞きつたへけり
水無月の洪水なせる日光のなかにうたへり麦刈少女
遠くゆきまたかへりきて初夏の樹にきこゆなり真昼日の嵐
木蔭よりんあぎさに出でう渚より木かげに入りぬ海鳴るゆふべ
松咲きぬ楓もさきぬはつ夏のさびしきはなの咲きそめにけり
郊外に友のめうとのかくれ住む家をさがして麦畑をゆく
夜のほどに凋みはてぬる夏草の花あり朝の瓶の白さよ
少女子の夏のころもの襞にゐて風わたるごとにうごくかなしみ
母となりてやがてつとめの終りたるをみなの顔に眼をとめて見る
夏深しかの山林のけだもののごとく生きむと雲を見ておもふ
麦の穂の赤らむころとなりにけりひと棄てしのちのはつ夏に入る
いつ知らず夏も寂しう更けそめぬほのかに合歓の花咲きにけり
わがこころ動くともなく夏草に寝居つつ空の風にしあがふ
夏草の延び青みゆく大地を静かに踏みて我等あゆめり
深草の青きがなかに立つ馬の肥えたる脚に汗の湧く見ゆ
夏白昼うすくれなゐの薔薇よりかすかに蜂の羽音きこゆる
わが友の妻とならびて椽に立ち真昼かへでの花をながむる
麦畑の夏の白昼のさびしさや讃美歌低くくちびるに出づ
黄なる麦一穂ぬきとり手にもちて雲なきもとの高原をゆく
高原や青の一樹とはてしなき真白き道とわがまへに見ゆ
麦畑のなかにうごける農人を見ゐつつなみだしづかにくだる
わが顔もあかがねいろに色づきぬ高原の麦は垂穂しにけり
ひややかに涙はひとりながれたりこころうれしく死なむとおもふに
われみづから死をしたしくおもふころ誰彼ひとのよく死ぬるかな
火の山にけむりは断えて雪つみぬしづかにわれのいつか死ぬらむ
渚より海見るごとく汪洋とながるる死のまへにたたずむ
夏白昼あるかなきかのさびしさのこころのうへに消えがてにする
松葉散る皐月の暮の或るゆふべをんな棄てむと思ひたちにき
影のごとくこよひも家を出でにけり戸山が原の夕雲を見に
皐月ゆふべ梢はなれし木の花の地に落つる間のあまきかなしみ
ひとつひとつ足の歩みの重き日の皐月の原に頬白鳥の啼く
日かげ満てる木の間に青き草をしき梢をわたる昼の風見る
見てあればかすかに雲のうごくなり青草のなかにわれよこたはる
わがいのち空に満ちゆき傾きぬあなはるかなりほととぎす啼く
たそがれの沼尻の水に雲うつる麦刈る鎌の音もきこえ来る
なつかしさ皐月の岡のゆふぐれの青の大樹の蔭に如かめや
落日のひかり梢を去りにけり野ずゑをとほく雲のあゆめる
けむりありほのかに白し水無月のゆふべうらがなし野羊の鳴くあり
わが行けばわがさびしさを吸ふに似る夏のゆふべの地のなつかし
麦すでに刈られしあとの畑なかの径を行きぬ水無月ゆふべ
椅子に耐へず室をさまよひ家をいで野に行きまたも椅子にかへりぬ
野を行けば麦は黄ばみぬ街ゆけばうすき衣ををんな着にけり
やうやうに恋ひうみそめしそのころにとりわけ接吻をよくかはしける
強いられて接吻するときよ戸の面には夏の白日を一樹そよがす
いちいちに女の顔の異るを先づ第一の不思議とぞおもふ
六月の濁れる海をふとおもひ午後あわただし品川へ行く
とかくして動きいでたる船虫の背になまぐさき六月の日よ
月いまだひかりを知らず水無月のゆふべはながし汐の満ち来る
海のうへの月のほとりのうす雲にほのかに見ゆる夏のあはれさ
少女等のかろき身ぶりを見てあればものぞかなしき夏のゆふべは
いささかを雨に濡れたる公園の夏の大路を赤き傘ゆく
いたづらに麦は黄ばみぬ水無月のわがさびしさにつゆあづからず
八月の街を行き交ふ群衆の黙せる顔のなつかしきかな
とこしへの逢ふこと知らぬむきむきのこころこころの寂しき歩み
あめつちに独り生きたりあめつちに断えみたえずみひとり歌へり
六七月の頃武蔵国多摩川の畔なる百草山に送りぬ、歌四十六首。
涙ぐみみやこはづれの停車場の汽車の一室にわれ入りにけり
ともすればわが蒼ざめし顔のかげ汽車のガラスの戸にうつるあり
雨白く木の間にけぶる高原を走れる汽車の窓によりそふ
水無月の山越え来ればをちこちの木の間に白く栗の咲く見ゆ
とびとびに落葉せしごとわが胸にさびしさ散りぬ頰白鳥の啼く
たそがれのわが眼のまへになつかしく木の葉そよげり梟の啼く
夕山の木の間にいつか入りも来ぬさだかに物をおもふとなしに
あをばといふ山の鳥啼くはじめ無く終りを知らぬさびしき音なり
わがこころ沈み来ぬれば火の山のけむりの影をつねにやどしぬ
檜の林松のはやしの奥ふかくちひさき路にしたがひて行く
青海のうねりのごとく起き伏せる岡の国ありほととぎす行く
わが死にしのちの静けき斯る日にかく頬白鳥の啼きつづくらむ
紫陽花のその水いろのかなしみの滴るゆふべ蜩のなく
煙青きたばこを持ちて家を出で林に入りぬ雨後の雫す
拾ひつるうす赤らみし梅の実に木の間のゆきつつ歯をあてにけり
かたはらの木に頬白鳥の啼けるありこころ恍たり真昼野を見る
日を浴びて野ずゑにとほく低く見ゆ涙をさそふ水無月の山
松林山をうづめて静まりぬとほくも風の消えゆけるとき
真昼野や風のなかなるほのかなる遠き杜鵑の声きこえ来る
梅雨晴の午後のくもりの天地のつかれしなかにほととぎす啼く
山に来てほのかにおもふたそがれの街にのこせしわが靴の音
或るゆふべ思ひがけなくたづね来しさびしき友をつくづくと見る
幹白く木の葉青かる林間の明るきなかに歩み入りにき
わが行けば木木の動くがごとく見ゆしづかなる日の青き林よ
かなしめる獣のごとくさまよひぬ林は深し日は狭青なり
はてしなくあまたの岡の起き伏せり眼に日光の白く満つかな
別るべくなりてわかれし後の日のこのさびしさをいかに追ふべき
棄て去りしのちのたよりをさまざまに思ひつくりて夜夜をなぐさむ
ゆめみしはいづれも知らぬ人なりき寝ざめさびしく君に涙す
遠くよりさやさや雨のあゆみ来て過ぎゆく夜半を寝ざめてありけり
ゆくりなくとあるゆふべに見いでけり合歓のこずゑの一ふさの花
きはみなき旅の途なるひとりぞとふとなつかしく思ひいたりぬ
六月の山のゆふべに雨晴れぬ木の間にかなし日のながれたる
ゆふぐれの風ながれたる木の間ゆきさやかにものを思ひいでしかな
ゆふ雨のなかにほのかに風の見ゆ白夏花のそぼ濡れて咲く
放たれし悲哀のごとく野に走り林にはしる七月のかぜ
松林風の断ゆればわがこころふるへておもふ黒髪の香を
かなしきは夜のころもに更ふる時おもひいづるがつねとなりぬる
鋭くもわかき女を責めたりきかなしかりにしわがいのちかな
七月の山の間に日光は青うよどめり飛ぶつばめあり
午後晴れぬ煙草のあまさしとしとに胸に浸む日ほととぎす啼く
暈帯びて日は空にあり山山に風青暗しほととぎす啼く
生くことのものうくなりしみなもとに時におもひのたどりゆくあり
うち断えて杜鵑を聞かずうす青く松の梢に実の満ちにけり
わがこころ静かなる時つねに見ゆ死といふもののなつかしきかな (以上)
秋風吹くつかれて独りたそがれの露台にのぼり空見てあれば
いつ知らず重ねて胸に置きたりし双のわが手を見れば涙落つ
このごろの迷ひ乱れにありわびて寂びしやわれに帰らむとする
しづやかに大天地に傾きて命かなしき秋は来にけり
まれまれに云ひし怨言のはしばしのあはれなりしを思ひ出づる日
物をおもふ電車待つとて十月の街の柳のかげに立ちつつ
公園の木草かすかに黄に染みぬ馴れしベンチに今日もいこへる
松虫鳴きそよ風わたるたそがれの小野の木の間を過ぎなやむかな
日は黄なり斑班として十月の風みだれたる木の間に人に
栗の樹のこずゑに栗のなるごとき寂しき恋を我等遂げぬる
たはむれのやうに握りし友の手の離しがたかり友の眼を見る
髪ながく垂れて額の蒼を掩ふ無言よ君にくちづけてゐむ
野には来ぬこころすこしもなぐさまず木の間を行きつ草に座りつ
ふるさとのお秀が墓に草枯れむ海にむかへる彼の岡の上に
波白く断えず起れる新秋のとほき渚に行かむとぞおもふ
けふ別れまた逢ふこともあるまじきをんなの髪をしみじみと見る
こころ永く待つといふなりこころ永く待つといふなりかなしき女
冷やかに部屋にながるる秋の夜の風のなかなり我等は黙す
こころ斯く荒みはてぬるわが顔のその唇をおもふに耐へず
秋の白昼風呂にひたりて疲れたる身はおもふなり女のことを
破れたるたたみのうへに一脚の寝椅子を置きつ秋の夜を寝る
うまき肉たふべて腹の満ちぬれば壁にもたれてゐねぶりをする
酔ふもまたなににかはせむすべからく酒を棄てむとおもひ立ちにき
二階より更けて階子をくだる時深くも秋の夜を感じぬる
おもはるるなさけに馴れて驕りたるひとのこころを遠くながむる
手をとりて心いささかしづまりぬもの言へば弥寂しさの増す
秋のあさうなじに薄く白粉の残れるを見つつ別れかへりぬ
わがちさき帽のうへより溢れ来る秋のひかりに血は安からず
健やかに身はこころよく饑ゑてあり野菊のなかに日を浴びて臥す
四階よりのぞめば街の古濠にゆふべ濁りて潮のさし来る
靴屋あり靴をつくろふ鍛冶屋ありくろがねを打つ秋の日の街
くちもとのいふやうもなく愛らしきこの少年にくちづけをする
わかくさの山の麓は落葉せむいまか静かに鹿の歩まむ
秋風吹き日かげさやかに流れたる窓にふたりは旅をおもへり
或時はなみだぐみつつありし日の寂しき恋にかへらむとする
はてしなくひろき林に行かしめよしばし落葉の音を断たしめよ
彼のとほき林に棲める獣はかなしめる日の無きかあらじか
われ死なば林の地を掘りかへしひとに知らゆな其処に埋めよ
林には一鳥啼かず木のかげにたふれて秋に身を浸し居り
涙落つまぬかれがたき運命のもとにしづかに眼を瞑ぢむとし
棄て去りしわが女をばさまざまに人等啄むさまの眼に見ゆ
かへり来よ桜の紅葉散るころぞわがたましひよ夙く帰り来よ
しかれども一度恋に沈み来しこのかなしさをいかに葬らむ
さまざまの女の群に入りそめぬ恋に追はれし漂泊人は
ことごとく落葉しはてし大木にこよひ初めて風のきこゆる
晴れわたる空より樹より散りきたるああ落葉のさまのたのしさ
かきいだけば胸に沈みてよよと泣くそのかみの日の少女のごとく
妻つれてうまれし国の上野に友はかへりぬ秋風吹く日
木木のかげまだらに落ちてわが肩に秋の日重し林に死なむ
彼の国の清教徒よりなほきよく林に入りて棲まむともおもふ
ありつる日死をおもふことしげかりし身は茫然と落葉を見る
山陰に吸はれしごとく四五の村巣くへる秋の国に来にけり (以下伴二と旅に出でて)
名も知らぬ河のほとりにめぐり来ぬけむり流るる秋の夕に
白々とゆふべの河の光るありたひらの国の秋の木の間に
雲うすく空に流れて凪ぎたる日林の奥に落葉断えせず
落葉樹まばらに立てる林間の地平にひくし遠山の見ゆ
身を起しまた忍びかに歩をやりぬ落葉ばやしの奥の木の間を
手ふるればはららはららと落葉す林のおくの黄なる一もと
林間の落葉を踏みつ樹に倚りつ涙かきたれなにを歌ふぞ
ながながと地上に身をば横へぬ夕陽の前の落葉林に
かきあつめ白昼落葉に火をやりぬ林の奥へ白き烟す
ひややかに落葉林をつらぬきて鉄路走れり限りを知らず
うす甘き煙草の毒に酔ひはてぬ黄なる林の奥の一人は (以上)
軒下の濠のひびきと硝子戸のゆふ風の音と椅子に痛める
夕暮のそよ風のなかにいたみ出づ倦みし額に浮ける蒼さは
新しき鵞ペンに代へしゆふぐれの机のうへに満てるかなしみ
ゆふぐれは蒼みて来りまた去りぬ窓辺の椅子にわれの埋るる
ゆふ日さし窓の硝子は赤赤と風に鳴るなり長椅子に寝る
数知れぬ女の肌に溺れたるこのわかき友は酒を好まず
打ち連れて活動写真観に行きし女のあとに灯をともすなり
果実をあまたたうべし夕まぐれ飯の白きを見るは眼痛し
家家にかこまれはてしわが部屋の暗きにこもりストーヴを焚く
悲しげに赤き火を見せゆふ闇の椅子に人あり煙草は匂ふ
黒髪の匂ふより哀しつかれたる身にゆふぐれのいどみ寄るさま
海に沿ひ山のかげなるみだらなる温泉町に冬は来りぬ
涙たたへ若かる友はかなしみぬ見よわが恋は斯くもまつたし
容れがたし一度びわれを離れたる汝がこころはまた容れがたし
白白と鷗まひ出づる山かげの冷き海をおもひ出でけり
離れたる愛のかへるを待つごときこの寂しさの咒ふべきかな
この河の流れて海に入らむさま蘆の間におもひ悲しむ
灯をともさむとする横顔の友の疲れは闇に浮き出づ
命なりそのくちびるを愛せよと消息に書き涙落しぬ
衰へしひとの額をかきいだき接吻せむとすればあはれ眼を瞑づ
半島の国の端なる山かげのちさき港に帆を下しけり (以下旅に出でて)
枝垂れ咲けり暗緑色の浪まろぶ海の岸なる老樹の椿
青き白き濤のみだれにうちまじり磯に一羽の小鳥啼くあり
ひろびろと光れる磯に独りゐて貝ひろふ手に眺め入りぬる
越え歩りく海にうかべる半島の冬のうす黄の岡より岡へ
旅人は海の岸なる山かげのちひさき町をいま過ぎるなり
海岸のちひさき町の生活の旅人の眼にうつるかなしさ
男あり渚に船をつくろへり背にせまりて海のかがやく
ゆふ日赤き漁師町行きみだれたる言葉のなかに入るをよろこぶ
風凪ぎぬ夕陽赤き湾内の片すみにゐて帆をおろす船
わが船は岬に沿へり海青しこの伊豆の国に雪のつもれる
夕陽の赤くしたたる光線にうかび出でたり岬の街は
春白昼ここの港に寄りもせず岬を過ぎて行く船のあり (以上)
編集上の注記
以下は編集作業の記録および注記です。底本に記載されているものではありません。
作業履歴
- 作業開始日:2021年4月26日
- 入力:2021/4/26 – 2021/5/3(月岡烏情)
- 入力者による初校:(未実施)
- 他者による二校:(未実施)
注記
- 原著は吾亦紅(われもかふ)とあるが(われもかう)とする。
- 166ページ、1首目の左注の一字が不明瞭のため確認が必要。
- 181ページ、わが脈搏に
- 183ページ、1首目「をもしろき」は「おもしろき」の間違いか。
- 218ページ、2首目「つぬに」は「つねに」の間違いか。
- 246ページ、「帽」の漢字は異体字。
- 257ページ、「衰」の漢字は異体字。
参考
- 国文学研究資料館 近代書誌・近代画像データベース 別離